オグたん式「F1の読み方」
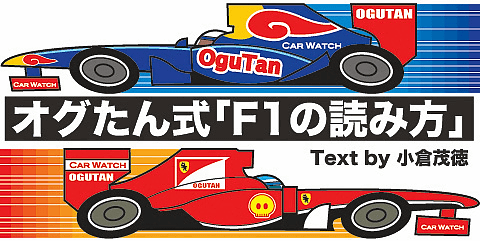
今年のF1が抱えた矛盾
(2014/5/30 18:54)
2014年のF1=理想と現実の狭間で
そもそも今年のF1はとても高い理想を追っていた。エンジンはV6ガソリン直噴ターボになり、瞬間的に流れるガソリンの流量とレース中に使えるガソリンの総量を規制することで、高効率なエンジン技術を創ろうとしている。簡単にいうとガソリン1Lからどれだけたくさんのパワーを取り出せるかということを追求しようとしているのだ。
さらに、F1は昨年までの「KERS(運動エネルギー回生システム)」から、今年はそれをより発展させた「ERS-K」となった。その中で、KERS同様にブレーキング時に車体が前に進もうとする勢いを利用して発電させ、これで減速を助けると同時に加速時のモーターによるパワーアシストにも利用するという方法をより高性能化した。これはハイブリッド車の性能向上には重要な技術だ。
さらにさらに、今年のF1では「ERS-H(熱エネルギー回生システム)」としてターボチャージャーに発電機を装着して排気ガスの勢いを利用して発電し、これもパワーアシストとして利用しようとしている。これは、70年ほど前に航空機用ピストンエンジンで考えられながら、ジェット化の波の中で打ち捨てられた「ターボコンパウンド」という排気ガスの力を動力として取り出す技術を、現代の技術で発電に利用しようとするもの。
これらはみな、ガソリンエンジンを利用しながら、より少ないガソリンからより多くのパワーを取り出し、環境負荷を少ない自動車を生み出すことにつながり、F1が“走る実験室”に戻るという、高い理想を実現したのだ。
今年のF1が抱えた矛盾
だが、これには大きな矛盾があった。
まず、こうしたエンジンと動力装置の開発には莫大な資金と労力が必要であることだ。F1は今、スポンサーの離脱と資金不足が問題になっている。そうした中でこの動力装置の導入はチームにとって大きな負担になってしまう。自動車メーカーが直接参加してくれるワークスチームはまだよいが、有料で動力装置の供給を受けるチームには費用負担が大きくなってしまいかねない。インディカーのようにエンジン供給価格の上限指定がないからだ。
しかも、動力装置の変更にともない、マシンの設計開発を大きく変更しなければならず、これもチームの負担を大きくした。とくに下位チームにはこれが厳しくのしかかっているようだ。
中でも、ブレーキと回生の協調制御はどのチームも苦労している。F1では回生(発電)を後輪で行うが、回生するときには後輪の回転しようするエネルギーが発電によって奪われる。すると後輪にはエンジンブレーキがかったような状態になる。そこにそのまま通常のブレーキをかけてしまうと、後輪は簡単にロックしてしまい、マシンはリアが暴れてスピンしやすくなってしまう。そこで、昨年まではドライバーが手動でレバーを操作し、ブレーキの利き方の前後バランスを変更することで対応していた。
一方、今年は回生するエネルギー量が大きくなり、後輪はよりエンジンブレーキが強くかかったようになる。これに対応するため、ブレーキの前後バランスは電子制御で自動化できるようになった。技術開発的には素晴らしいことだ。
だが、これを完璧に実現するのはとても難しく、多くのテスト時間が必要だ。WEC(世界耐久選手権)ではトヨタ自動車がこうしたシステムを2012年から導入し、その時点でトヨタはハイブリッド車で回生とブレーキの協調制御に先進的な技術を持っていた。それでも、2012年のWEC導入当初はその精度に苦しみ、完成までには多大なテスト走行と開発作業を必要とした。ところが、F1は今年の開幕前の延べ12日間だけしか走行テストができなかった。これではいかに高い技術力を誇るF1チームでも無理があった。
結果、開幕戦の小林可夢偉のスタート直後のクラッシュに代表されるように、ブレーキの不具合やブレーキと回生の協調がうまくないために、ブレーキングでミスするシーンが予選や決勝でも増えたのだ。
ただ、素晴らしいのはF1ドライバーたちの適応能力の高さだ。今年のF1のブレーキシステムはブレーキペダルが電気スイッチになっていて、ドライバーのペダル操作はコンピューターを介してブレーキ作動装置につながっている。昨年までのようにブレーキペダルとブレーキがブレーキ液で直結していないので、ブレーキの様子や感覚がドライバーの左足には伝わってこない。それでもドライバーたちは限界ギリギリの高いブレーキ性能を引き出しながら走っている。
そんなシステムなので、モナコGPの予選でニコ・ロズベルグがブレーキをミスして黄旗を誘発し、ルイス・ハミルトンら他のドライバーが予選の最後のアタックができなくなったのも致し方ないといえる。もちろん、ロズベルグはタイムアタックのためにブレーキングを遅らせたわけだが、昨年までとは異なり、その操作はより難しくなっているのだ。
このブレーキの問題は今後も大なり小なり続くだろう。これを解消するには充分な走行テストが必要だ。走行テストは昨年より緩和されたとはいえ、まだ制限されている。もしも制限を解除したら、今度はチームには莫大なテスト走行費用の負担が重くのしかかってしまい、チームの財政状態による実力差がより拡大するか、費用負担の増大でチームの倒産につながりかねない。
こうした高い理想と現実のジレンマは、ノーズにも現れている。衝突時にハイノーズでは相手のドライバーのヘルメットにノーズが直撃する恐れがあったので、今年から低いノーズとした。また、ハイノーズでは追突時に相手のリアタイヤに乗り上げて飛ばされやすいという実験研究事実も、2010年にFIAが発表していた。
理想はよかったが、実際のルールの書き方がよくなかったために、あのような奇抜でルールをないがしろにした「脱法的」ですらあるようなノーズが出てきてしまった。
どうにもならない音の問題
今年のF1で多くのファンから問題とされているのが、ターボエンジンの音の問題だ。これの対策として、スペインGP直後のバルセロナテストでメルセデスのマシンにメガホン型の排気口をテストした。これで音を「少しでも」大きくしようと試みた。だが、結果はやはり「少しでも」程度の変化だった。この問題はどうにもできないのかもしれない。というのも、ターボチャージャーがより効率よく排気ガスを利用しているからだ。
ターボチャージャーは、排気ガスの勢いを利用してタービンという風車を回し、これでコンプレッサーという風車を回してエンジンに送り込む吸気を加圧する。こうすることで、より多くの酸素をエンジンに送り込み、より圧縮させて、より大きなパワーをエンジンから取り出せるようにしている。
より大きなパワーを取り出すには、より多くの空気をエンジンに送り込みたい。すると、直前に記したターボチャージャーの働きをより高めたくなる。結果、排気ガスの勢いをよりうまく使おうとする。加えて、今年のF1では「MGU-H」として排気ガスの勢いで発電もしようとしているので、排気ガスの勢いをさらに使うようになる。
排気ガスの勢いは、簡単にいうと排気音の元と考えていただいてもよいだろう。つまり、排気ガスの勢いをターボチャージャーと発電で使うことは、排気音の元を使っていることになる。放出される排気ガスを再利用することは、動力装置の効率を上げて燃料から取り出せるエネルギーをより増やすことになり、環境負荷を減らすためにもよりよいことだ。その半面、音の元はどんどん減らされることになる。そのため、大きなラッパを着けたとしても、その効果は限定的でしかない。まるでトランペッターの肺活量が落ちて音が小さくなったからと、トランペットの先を大きなラッパにしたようなもので、肺活量を上げる以外に効果は大したことはないのだ。
では対策は? となると、大きく分けると2つしかない。1つはこのレギュレーションをやめてエンジンを自然吸気に戻すこと。これは確実に音が大きくなる。だが、環境対策技術開発という理想を捨てることになる。もう1つは現在の音を「新たな技術と時代の音」として現実を受け入れるかだ。WECでは後者の方法をより追求し、アウディのディーゼルターボは高効率を極めたおかげで排気音がほとんど聞こえないほどだ。
そんな中、インディカーやスーパーフォーミュラのターボエンジンでは、エンジン自体での効率追求と技術開発は促しても、ターボチャージャーは指定のものとすることで音をある程度確保すると同時に、ターボチャージャーの開発にともなう莫大な費用負担もさせないようにしている。これは音も確保しながら技術開発もするという、両方の選択肢の間でうまいバランスを探ろうとする方法だ。
自動車メーカー参戦確保のため?
環境負荷が少ないエコロジカルで、ユーザーの燃料代負担も少ないエコノミックな、より「エコ」なクルマを実現する新たな時代の自動車を開発するための“走る実験室”。今年のF1はこの理想をより高いところに設定して、実行しようとしている。こうすることが自動車メーカーの参戦確保にもつながると信じられた。
だが、莫大な開発費用負担という問題もでてきた。そこで、FIAは2013年の夏に今年のF1エンジンにも従来と同様のホモロゲーションルールを設けた。それは、エンジンは開幕戦時点の状態のままとして2020年まで設計変更ができないというもの。
これは新しい問題を生んだ。この規定によって、エンジン開発は2013年までと同様にコンピューターなど一部の変更しかできなくなってしまった。2013年までの開発しつくされたエンジンならまだしも、開発が必要なエンジンでこのルールは厳しい。メルセデスは素性のよいエンジンを投入でき、フェラーリもそこそこだった。
一方、開幕からトラブル続きのルノーは苦しみ続けている。エンジン本体の設計変更など大きな開発の余地がなければ、ルノーはこの問題から抜け出せないままでその差を大きく埋めることは難しいだろう。フェラーリとルノーはこのままいつまでもメルセデスとの性能差に甘んじながら参戦を継続するだろうか? だが、当初の理想だった高効率エンジン開発のための大幅な開発と設計変更を許してしまうと、それは競争の中で大金をつぎ込んでしまい、やはり撤退の危機に陥るというジレンマもある。
本田技研工業は来年からF1に参戦するが、当初はこの高効率なエンジン技術の開発を参戦の目的の1つとして掲げていた。そして、ホンダが正式に参戦を発表して後戻りできない状況となったあとに、FIAはこのホモロゲーションルールを導入し、設計変更と大幅な開発の凍結を決定してしまった。これは、傍観者である筆者から見るとFIAによる後出しじゃんけんのようにも見えた。
開発競争とコスト抑制と存続のバランス、その理想像は日本にあり?
F1の規定では、エンジンに信頼性や安全性やコストの問題がある場合は例外として設計変更が可能とされている。ルノーがライバルとの性能差を埋めるために、この例外を利用するかもしれない。だが、それにもやはりコストがかかってしまうし、FIAの承認もいる。
では、F1はどうしたらよいのだろう?
開発や参戦コストの増大を避けたいのであれば、高効率エンジンやハイブリッドの技術開発という“走る実験室”の立場はWECに任せ、F1はシンプルなマシンとして、もっぱらドライバーの技量を競うというフォーミュラ本来の目的に合致したマシンとするという選択肢もあるかもしれない。これは、第二次大戦直後にFIAが理想とした、均質な車両でドライバーの技を競う車両である「フォーミュラ」本来のあり方に合致するものにもなる。そうすれば、エンジンを自然吸気にもできて音がよくなるかもしれない。しかし、開発の「大義」を失うと自動車メーカーの参戦を促すのは難しくなる。すると、F1はGP2のようなワンメイクのフォーミュラになるかもしれないし、参戦コストが小さくなると同時に、華やかさが減るかもしれない。
それとも、チームとシリーズの存続の危険性を度外視して、いつ撤退するかも分からない自動車メーカーの姿勢に頼りながら、コスト度外視でWECのLMP1-Hのように費用と労力を大量に投入して開発をどんどん進めるのか? F1の行くべき道を考える時がきているようにも見える。
この問題を解決する答えとして、インディカーはよい方向性を示しているように思える。それは、開発を大幅に制限してよりドライバーの技を競うものにしているからだ。
そして、日本のスーパーフォーミュラはこうした方向でより理想的なものを追求している。スーパーフォーミュラの規定では、エンジンは3イベント連続で使うとされ、第1戦から第3戦までと、第4戦から最終戦まで、それぞれ各1基を連続で使うこととされている。いいかえると、開幕戦から第3戦までのエンジンと、第4戦からのエンジンとでは、本体の設計変更と進化が可能ということなのである。この設計変更には細部の制約も加えることで、コスト抑制をかけながらも、開発と改善の余地が残るようにされている。
実際、今年のスーパーフォーミュラの序盤戦ではトヨタとホンダでエンジン性能差が大きく出てしまっている。しかし、第4戦からのエンジンはまだ分からない状態だ。ホンダはトヨタに追いつき追い越そうとし、トヨタはホンダをさらに引き離そうとしている。こうした自動車レースの持つ技術開発競争としての面白さも残されている。そして、その技術開発はエンジンそのものの高効率燃焼と、より「エコ」で走りが楽しい近未来の自動車実現のための“走る実験室”への道をより速く進むことにも直結している。
スーパーフォーミュラのエンジン規定とその施行方法は、F1にとってその高い理想をバランスよく実現するためのよい手本となりそうだ。思い起こせば、この20年間のF1の安全性能向上も、インディカーやNASCARとの情報交換が大きく貢献していた。コストと開発と競技としての面白さのバランスという点でも、F1はよりプラグマティック(実利的)になって、誇りよりも他でよいものがあれば積極的に学び取り入れることが、その未来にとっては重要なのではないか。その理想とブランド力はまだ素晴らしいのだから。
ドライバーのライバル関係については?
最近、ニコ・ロズベルグとルイス・ハミルトンなどチーム内のライバル関係が話題になりつつある。これを1980年代末から1990年代前半のアイルトン・セナとアラン・プロストとの関係になぞらえるメディアの姿勢もうかがえる。
当時のプロストとセナと同じチームにいた筆者にとっては、“現代の2人”が一部のメディアが伝えるように“かつての2人”と同じような関係なのかどうかはもう少し状況を見てみたいところだ。ただ、今いえることは、この2人の関係はこの2人にしか分からないもので、周囲の想像の大部分は邪推に過ぎないものが多いのではないかということだ。それは、プロストとセナの時代もそうだった。そして、ハント対ラウダの時代もそうで、そのことは映画「ラッシュ」でも描かれていた。
面白さと希望が増したスーパーフォーミュラ
一方、国内に目を転じると、先述のスーパーフォーミュラは希望と面白さが増した。マシンは新型のSF14となり、その軽量で優れた空力性能によって、接近戦とバトルが可能となった。開幕戦の鈴鹿では至る所でバトルと追い抜きが可能となった。第2戦の富士では2レースの超スプリント戦としたために追い抜きがやや減ったが、それでも追い抜きやバトルが2013年よりもはるかに増えた。
F1やWECでは今年から燃料流量規制が導入されているが、そもそもこの燃料流量規制を最初に提唱したのは日本(スーパーフォーミュラと、同じエンジンを利用するSUPER GT)だった。そして、その規制方法もセンサーで計測するのではなく、独自の燃料流量リストリクター(流量規制装置)で行っている。これはトヨタ、ホンダ、日産自動車の共同開発で、その製造とメンテナンスはケン・マツウラ・レーシングが行っている。いわば、日本のレーシングエンジン技術の最高峰が集まって結実させたものである。
果たしてでき上がった燃料リストリクターは小型軽量ながらシンプルな構造で、極めて高い精度を発揮。SUPER GTでもスーパーフォーミュラでも、その誤差は限りなくゼロである。しかもトラブルフリーで、オーバーテイク用の燃料流量増量装置(5%増量)部分がついたスーパーフォーミュラ用でも毎戦トラブルなしで、スペアはスペアのまま週末を終えている。そして、このリストリクターはくじ引きでチームに渡され、各部に封印もされているため、不正をする余地もない公平なものになっている。おかげで、F1の開幕戦で起きた燃料流量センサーにともなうダニエル・リカルドの失格騒ぎも起きない。
WECは、F1で使っているのと同じ燃料流量センサーによる規制方法をとっているが、F1チームと同様にその精度に疑心暗鬼になっているマニュファクチャラーもいる。これはF1の開幕戦でのリカルド失格の問題で現れたように、競技の公平性という点で興ざめなことが起きる危険性もはらんでいることになる。特に走行距離と燃料消費量の多いル・マン24時間ではその不安は大きいともいえる。もちろん、問題もなく上手くいくことを願っている。
今年のスーパーフォーミュラに話を戻すと、よりエキサイティングな接近戦と追い抜きが増えたうえに、より速いコーナリングで刺激的な走りができ、国内だけでなくヨーロッパなど海外からの注目も高まっている。おかげで、ドライバーの層もより厚くなり始めている。さらに、その高効率な直4ガソリン直噴ターボエンジンと高精度な燃料流量リストリクターなどの技術は極めて高度で堅実であり、まさにより現実味を帯びた近未来の自動車のための“走る実験室”としての道を歩んでいる。
F1はもちろん素晴らしく、日本GPではサーキット入場者全員に小林可夢偉の応援フラッグが配られるという魅力的で素晴らしい演出もある。それと合わせて、今改めて国内のレースに目を向けるのに絶好の時期だと思う。ぜひサーキットでその走りとバトルをご覧いただければと思う。技術と戦略はF1に迫る高度さで、スーパーフォーミュラのコーナリングスピードはF1に優るとも劣らない。鈴鹿でのラップタイムは昨年のF1のQ1勢を凌いでいる。SUPER GTもより高性能になり、新型GT500はF3のラップタイムを上回るほどだ。
国内レースは観戦費用もF1よりはるかに低コストで気軽に楽しめる。観戦の充実度もきっと高いはず。これから国内選手権も各地で展開される。国内レースのよさを知ることは、F1が持つ華やかさや、WECが持つ独自性などをより際立って感じることにもつながるだろう。実際、筆者はこれを実感している。
国内レース、オススメだ。
