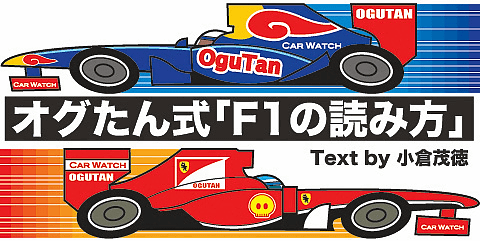 |
トヨタF1撤退は、モータースポーツ新時代への胎動
 |
| F1撤退を発表する豊田章男社長(右)と山科忠専務取締役兼トヨタF1チーム代表(11月4日) |
昨年12月のホンダ、今年の7月BMWについで、トヨタもF1から撤退を発表した。
ファンにとって、F1から自動車メーカーが離れて、シリーズに陰りが出そうになる事は残念なことだ。だが、こうして撤退していったメーカーの態度は、企業の経営判断としてはいずれも正しいといえる。見方を変えると、むしろ健全な判断であったと言えるかもしれない。
■異常なF1と健全な経営判断
現代のF1はとても豪華で刺激的だが、異常なほどに高コストなものになっている。年間参戦費用は約500億円ともいわれる。だが、これでも自動車メーカーにとって、投資に見合う見返りがあればまだ良かった。しかし、現代のF1は自動車メーカーにとってF1参戦の意義はかなり薄いものになっている。
F1のテクノロジーは極めて特殊化し、市販車への技術フィードバックはほとんどなくなってしまった。数少ない例外的なものとして、1990年代から進められたF1の衝突安全研究の成果が、ユーロNCAPをはじめとした市販車の衝突安全基準に応用され、市販車の衝突安全性能が高まったことくらいだ。また、今後の技術として、カーボンファイバーによる軽量化と、それに伴う高いエネルギー効率、高強度と高剛性による高度な安全性を実現する車体技術くらいかもしれない。
F1の競技とルールを統括するFIA(国際自動車連盟)は、F1でも環境対策技術の「走る実験室」となるべく、今年KERS(運動エネルギー回生システム)を導入した。これは、開発と運用費用がかかったが、ハイブリッドや電気自動車で遅れた欧米メーカーには意味があった。研究が進んでいたメルセデス・ベンツは、Sクラスに高効率なリチウムイオン電池によるハイブリッド仕様を設定し、F1の技術的共通性を見せることで、より技術的価値とイメージを高めることにも成功していた。
また、電気自動車や燃料電池車に必要な関連技術や部品の開発促進にもつながるようにしたいという思惑もあった。だが、KERSは、F1チーム側がこれを来年から禁止する協定を結んでしまった。これには、費用の問題だけでなく、FIAとの政治的駆け引きの要素も多分に見え隠れしていた。
 |  |
| 左はマニエッティ・マレリ、右はメルセデス・ベンツのKERS用ユニット。メルセデス・ベンツはフランクフルトモーターショーで「F1ハイブリッド」としてKERSを展示し、アピールしていた | |
自動車メーカーにとって、F1参戦のもうひとつのメリットは、技術者の育成だろう。常に待ったなしの状況で、最適な判断を要求されることで、より明晰な思考、判断力を備えた人材が育つようにはなる。
しかし、現代のF1は企業イメージ宣伝のツールという側面がつよい。だが、これに年間500億円前後もかける意義があるのか?という声が社内から出てもおかしくない。たとえば、F1に参戦しても、レースや合同テストでの映像CMなどを宣伝には簡単に利用できないのだ。こうした映像使用には別途料金が発生し、きわめて高い。プライベートテストやプロモーション用の撮影は、テスト規制の中で大幅に制限され、撮影機会が少ない。しかも、サーキットは観客も装飾もなく、殺風景な中を走る映像になってしまう。
こう見ると、F1は自動車メーカーにとって、多額の投資に対して、広告宣伝としてのメリットはうすいと言わざるをえない。
■必ずいるモータースポーツ反対派
多額の費用がかかるモータースポーツには、どの企業にも反対派が内在する。モータースポーツ活動は、総務・財務部門から見れば無駄な支出となる。営業部門は、その予算を営業支援にまわせとなる。
世界中の自動車メーカーのなかで、モータースポーツ活動を聖域とできるのはフェラーリくらいだろう。筆者の経験でも、V6ターボ、V10、V12エンジンを投入してF1で大きな成功を収めていたときのホンダでさえ、「カネのムダ使い」としてF1に反対する声が社内から聞こえた。こうした人達の主張もまた、自動車メーカーの「本業」を考えたとき、理があるものだった。
先述のように現在のF1は市販車への技術フィードバックの可能性が少ない。F1など、多くのモータースポーツ活動は、企業イメージを担う広告宣伝媒体であり、その予算の大部分を広告宣伝費にかなり依存している。ところが、企業が業績不振になったとき、真っ先に削られるのは広告宣伝費なのだ。そうした中で、F1参戦費用の数百分の1以下の予算の企業スポーツチームも、廃部に追い込まれるところが多いのが実情だ。
 |
| NASCARは成功例の1つ |
■低コスト化への試み
アメリカの自動車メーカーのモータースポーツ部門は、こうした状況をよく理解している。そのため、戦績が市販車販売にかなりの関連性があるとされてきたNASCARをはじめ、アメリカのモータースポーツはあえてコスト上昇を防ぐルールを採用している。そして、なるべく1社が一人勝ちしない接戦状態にして大衆の人気と注目を集めることで、モータースポーツ反対派の役員たちに「撤退」の決断をさせにくくしている。
FIAのマックス・モズレー前会長は、こうした状況とその成功例を2004年にアメリカで開かれたSAE(米国自動車技術者協会)の学会に参加した際に聞き、F1などFIAの各チャンピオンシップに取り入れようとしていた。だが、これはチーム、メディア、ファン、参戦メーカーからの激しい反対にあった。
それでもFIAは今年に入って、2010年から参戦コストの上限を1チームあたり4000万ポンド(約60億円)にすることを提案した。この金額は、90年代初期の時代のF1チームの費用から出したものだった。90年代初頭は、日本でF1大ブームのとき。F1はハイテク化につき進み始めたところ。当時この額でも参戦費用高騰が危惧されていたのだが、今はその10倍近い額がかかっている。まともな状況ではないだろう。
ところがチーム側の団体であるFOTAは、ウィリアムズとフォース・インディアを除く全チームがFIAのコスト上限制限案に反対した。これが6月のF1分裂騒ぎにまで発展した。最終的には、6月末の段階でFIAがコスト上限案を撤回し、FOTA側は2012年末まで全戦参戦を保証するという契約にサインすることになった。BMWは、この契約調印期限ギリギリの7月末に今季限りでの撤退を発表する事で、この契約から逃れていた。だが、トヨタはこれにサインをしていた。FIAは参戦契約をしたトヨタが撤退発表したことを問題視し、その日のうちに調査に入ると発表した。
トヨタは、BMWと同様に参戦契約調印前に撤退の意向を発表していれば、あるいはブリヂストンが2010年の契約期間満了をもって以後の契約更新の意向がないことを今発表することで、FIAに次のF1タイヤ供給先を探す猶予期間を与えたように、通告から実施まで猶予期間をあたえられれば、大きな問題にはならなかっただろう。企業としては早急の決断が必要で、経営判断としては正しかったが、ホンダとトヨタは、F1撤退の決定から発表までのプロセスが性急すぎて、エゴイスティックな印象を抱かれてしまったのはマイナスだった。反面早めにF1撤退の意向を発表したBMWとブリヂストンはとてもスマートで、周囲に好印象を残した。
 |
■動きがとりにくくなったルノー
ルノーも来期の展開が危ぶまれてきた。トヨタの撤退発表同日に、ルノーはパリで臨時役員会を開いた。役員会の議題にはルノーF1チームの今後も入っていたという。
その日の役員会を受けて、ルノーは欧州での電気自動車事業の拡充を発表した。ルノー・日産としてみれば、F1撤退で浮く年間数百億円規模の資金をもとに、人、カネ、モノを電気自動車事業に集中的に投入することで、電気自動車分野で一気にリードに転じたいはず。企業としても健全な判断だろう。
一方、ルノーF1チームはすでに来期のドライバーとしてロバート・クビサ、スポンサーとしてオランダの時計メーカーTWスティールと契約もしている。F1チームのスタッフたちにとって来季への動きを決めたことが、本社に対して活動停止とチーム解散を思いとどまらせる材料になることも期待されるところだろう。F1チームのメンバーにとっては、予算が減額されても活動継続、あるいは、新たな売却先での活動継続をすることで、職場と収入の確保を願っているはず。
だがルノーのカルロス・ゴーンCEOは「ルノーF1の来年については、年末に発表する」という発言にとどめた。おそらく、FIAのトヨタに対する出方を見ようという点もあるのだろう。ルノー本社は、どのような結論を出すのだろうか。
■そして誰もいなくなった?
6月に起きたFIA対FOTAの論争を現場で目の当たりにしたとき、筆者の頭の中にはアガサ・クリスティの小説のタイトル「The Ten Little Indians=そして誰もいなくなった」がめぐっていた。
FOTAの主張は威勢こそ良かったが、現実味が乏しい内容が多かった。しかも、FOTAの主要役員たちの大部分は、参戦している自動車メーカーから見れば、子会社のトップか1つの部門の責任者であって、組織の中ではトップが決定した経営方針に従わざるを得ない立場にすぎないものだった。すると、経営環境の悪化や、経営方針の転換があれば、F1担当者は無念さを表情や態度に出しても、それに従うしかない。自動車メーカーは自動車を開発、製造、販売するという「本業」を確保しなければならない。だから、モズレー前会長は「自動車メーカーは信用できない」「依存できない」と説いていた。
トヨタの撤退発表を受けてフェラーリは、「メーカーが相次いで撤退する状況になったのは、F1を運営してきた側、つまりFIAとF1のプロモーター団体であるFOAのありかたにも責任がある」という声明を出した。奇しくも、その中でまたアガサ・クリスティのあの小説が引用されていた。異常なF1のところで述べたことを考慮すれば、フェラーリの主張にも、一部に理がある。
 |
| クーパー・クライマックスT51(1959年) |
■「歴史は繰り返す」か?
だが、F1には新規参入チームが控えている。これらの多くは、FIAによるコスト上限制限案導入を期待して参入しており、FIAとFOTAとの合意でコスト制限が撤廃されたのはチーム運営への不安を招くものになっている。
フェラーリはこうした新興チームについて、F1チームとしての資質を満たしていないと非難する。
50年代後半のF1でも、自動車メーカーのチームが減る一方で、ロータス、クーパーなどイギリスの小規模コンストラクターが入って来ってきたときがあった。当時、エンツォ・フェラーリはイギリスのコンストラクターズを「ガレジスティ=自動車修理ガレージたち(つまり、自分で車両を設計開発、製造する能力がない連中)」と呼んで、蔑んだ。だが、フェラーリは、このガレジスティたちの創意と工夫に富んだマシンと技術の前に屈服することになった。
70年代前半には、排気ガス浄化対策と、石油ショックによる販売不振と低燃費車開発に追われて、自動車メーカーはレースから次々と消えていった。環境と低燃費と販売不振。現在と同様な状況だった。F1でも自動車メーカーチームはフェラーリだけとなり、あとはマトラがエンジンを供給する程度だった。
だが、F1はコンストラクターズによる黄金期を迎えていた。ロータス、ティレル、ブラバムなどのコンストラクターは、エンジンはコスワースのDFV、ギヤボックスはヒューランドと共通のものを使った。パワーユニットが共通になったことで、ライバルとの差をつけるために車体の技術を競うようになった。結果、空力など大幅な技術発展が起きた。
 |  |  |
| マクラーレン・コスワースM23(1973年) | シャドウ・コスワースDN5(1975年) | ウィリアムズ・コスワースFW07B(1980年) |
一方、マシンの性能差が少なく、ドライバーの腕があればマーチのような市販のF1マシンでも優勝が可能だった。しかも、そのマーチは、かなりの部品をF2やF3と共用する低コストな設計でもあった。ちなみに、このマーチの設立メンバーで、主に営業とレースチームの運営を担当していたのがモズレーだった。また、ブラバムチームのオーナーが、現FOAの代表バーニー・エクレストンで、チームの主要スタッフがチャーリー・ホワイティングとハービー・ブラッシュ、さらに現在のFIAのF1担当競技役員たちである。
新規参入チームがコスワースを多用する状況に、FIAの陰謀とするウワサがあったが、これはかなりうがった見方だろう。昨今の自動車メーカーがF1から相次いで撤退しそうな状況を予想していたFIAにとって、新規参入チームがエンジンを安定確保できるように先行き不透明な自動車メーカー製よりも、コスワース製を勧めるのは当然のこと。
70年代から80年代初頭にかけてF1を支えたコスワースエンジンは、大量に供給される中で、ニコルソン・マクラーレンなど、さまざまなペシャルチューン版DFVも生まれた。これで、エンジンチューナーに新たなビジネスチャンスを生んだ。コスワースエンジンがふたたび増えることは、こうしたチューナーたちにF1復帰の可能性が生まれる。ホモロゲーションエンジン規定のためシーズン中の開発は不可能だが、少なくともエンジンの組み立てなどの作業をコスワースから受託できる可能性はある、
また新規参入の中小規模チームは、車体などの部品製作でも外注率が高くなるとみられる。そのため、イギリスを中心としたモータースポーツ関連産業業界からは、自動車メーカーの撤退と新規チームの参入によって、ビジネスチャンスと雇用を創出する可能性が高まると、期待を寄せる声も聞こえている。
■F1チャンピオンシップの変遷
F1の原点は、1906年にル・マン市で開催されたACF(フランス自動車クラブ)グランプリとなる。以来、グランプリはヨーロッパを中心に各国で年1回だけ開催される最高峰の自動車レースの格式を与えられてきている。また、競技車両の規則として「フォーミュラ」という言葉も生まれた。そして、初期のころから最高のドライバーと自動車が集まり、そこには最先端の技術が投入されてきた。
とくに1930年代には、ベンツとアウトウニオン(現アウディ)がドイツ政府の支援を受けて、大きな技術進歩を成し遂げた。このドイツのシルバーアローたちに唯一対抗したのは、当時アルファロメオのチームだったスクーデリア・フェラーリ。シルバーアロー対赤いフェラーリの戦いの原点はここまでさかのぼる。
一方、より市販車に近い近未来の技術を競う場として、ル・マン市では24時間レースが1923年から開催されてきている。
 |  |  |
| 1934年のメルセデス・ベンツ(左)とアウトウニオン | アルファ・ロメオ8C 2300 ル・マン(1931年) | |
第2次大戦が終わるとすぐにFIAが結成され、2つのワールドチャンピオンシップが構想された。1つは、ドライバーの操縦技量を競うフォーミュラカーによるドライバーズチャンピオンシップ。もう1つは自動車メーカーの技術力を競うスポーツカーによるマニュファクチャラーズチャンピオンシップ。
ドライバーズチャンピオンシップのフォーミュラカーは、1人乗りで、レギュレーションによって束縛を強める事で、なるべく性能が均質な車両とすることで、ドライバーの力量が出やすいようにするという考えだった。F1は、こうしたフォーミュラカーの頂点に位置する車両だった。
FIAの当初の考えから行けば、自動車メーカーが最先端の自動車技術力を競う場は、ル・マン24時間に代表されるスポーツカーやスポーツプロトタイプカーで行われるマニュファクチャラーズ(メイクス)チャンピオンシップに分けられるべきだった。60年代後半には、こうした状況が実現しつつあった。
だが、排ガス対策と石油ショックでスポーツカーレースは衰退し、F1はプライベートチームの時代になった。当初は、マーチのような市販シャシーと大量に市販されたコスワースエンジンとヒューランド製ギヤボックスを組み合わせても勝てるチャンスがあった。だが同時期に、シャシーを自作するコンストラクターによるシャシー開発競争の時代になった。そして、シャシーは自作が義務付けになった。
80年代になると、F1はターボエンジン時代となり、自動車メーカーが戻ってきた。以来F1では、コンストラクターズチャンピオンシップも、より重視されるようになった。そして、人、カネ、技術がより集中するようになって、現在に至っている。
■F1グランプリの自己矛盾
1940年代末に構想された当時のF1の理想像は、現代ならGP2やフォーミュラ・ニッポンのように全車共通のワンメイクフォーミュラのようなものだったはず。しかし、第2次大戦で戦場となったヨーロッパでは、経済的に産業的にも疲弊し、資材も揃わなかった。そのため、規制の中でフォーミュカーを作って参加するメーカーやチームに頼るしかなかった。
結果、競争の中でF1は、1930年代以前のような、ドライバーの技量もクルマの技術もすべて競うものになった。だが、本来F1はドライバーの操縦技量の差を競うもので、性能差が少ないマシンが理想だった。ここに、F1はその成り立ちにおいて大きな矛盾を抱えていることになる。
また、少し前に議論されたシャシーを購入しても参戦できる「カスタマーシャシー制度」も、70年代前半の自動車メーカーが相次いで撤退していった時代に、中小規模のチームが比較的小さな予算で参戦することで、F1グランプリを支えた時代の復活を構想したものだった。
しかし、こうしたワンメイクに近くなるような、レギュレーションによる厳しい車両規制と、市販のカスタマーシャシーによる参戦形態は、ファンから「F1はインディカーではない」と、非難された。だが、歴史を振り返れば、これもF1なのであり、むしろ当初の理想形に近い姿なのかもしれない。
 |
| 1964年のインディカー「アルシエロ・ブラザーズ・スペシャル」 |
ちなみにインディカーは、かつて「○○・スペシャル」という車名が多かったように特製マシンによるレースだった。インディ500のエントリーがドライバー名ではなく、シャシー名優先なのもこうした歴史的経緯によるもの。つまり、インディカーの方が歴史的には、技術開発競争に積極的なレースな時期があった。だが、60年代末からの安全のための性能規制の中で、次第にマシンの技術競争からドライバーの競争にシフトし、現在はほぼワンメイクという状況におちついている。
「F1らしさ」「インディカーらしさ」というコトバの指し示す意味、実態、認識もまた、歴史の中で転換してきているのである。
■新たな時代への胎動
話を元に戻すと、メーカーはなくともF1が成り立った時代もあった。かえってドライバーの技量の差がより目立つようになったし、競争の中で独自の技術開発も行われ、マシンによる独り勝ちが減ったことで面白いシーズンもあった。
反面、現在は70年代初頭のように、自動車メーカーにとって不況による業績不振と環境対策技術への対応に迫られる冬の時代だ。
だが、冬が来れば春も続く。この冬が長引くのか、春がすぐに来るのかはわからないが、冬の夜長は思索をめぐられるのには絶好のときだ。植物は土の中でエネルギーを蓄えながら春を待つ。ホンダ、BMW、トヨタの撤退は、バブルのように浮かれていたF1とモータースポーツ界にとって、理想的なF1のありかた、モータースポーツのありかたをあらためて考え直すのに良い契機となるだろう。
一方、自動車メーカーは、自動車を販売する以上、自動車を使ったスポーツの楽しさをユーザーに提供・提案すべきで、どのカテゴリーでどのような活動をするのかは自由だが、モータースポーツ活動はなんらかの形で残すべきだろう。自動車メーカーが、モータースポーツを否定したら、これもまた自己矛盾になってしまう。
ル・マンは、環境対策技術の開発促進の場になるよう力を入れている。アメリカン・ル・マンは、昨年からSAE、EPA(合衆国環境保護庁)などと共同で、エネルギー効率の高い車両と技術を表彰するためのレギュレーションと制度も設けている。このほかにも、ソーラーカーの競技、電気自動車の競技、一般のドライバーが楽しめるレベルの競技、ハンデキャップドライバー向け操縦装置がついた車両による競技などと、モータースポーツには多様な広がりがあり、性別、年齢を超えてともに競技に参加し楽しめる可能性がある。
莫大な費用がかかるF1はやめても、他のモータースポーツ活動を残しているホンダ、BMW、トヨタのやり方は、F1のファンには残念かもしれないが、モータースポーツ全体という広い視野に立てば、新たな動力や技術や競技への発展や、より広い層への広がりと認知につながる可能性にもなり、とても正しいといえる。
 |  |  |
| F1撤退後も、ホンダはSUPER GT、BMWはWTCCなどへの参戦を続けているし、さまざまなモータースポーツをサポートしている。トヨタもそのほかの分野への参戦は継続すると表明している | ||
■URL
FIA(英文)
http://www.fia.com/
The Official Formula 1 Website(F1公式サイト、英文)
http://www.formula1.com/
■バックナンバー
http://car.watch.impress.co.jp/docs/series/f1_ogutan/
(Text:小倉茂徳)
2009年 11月 10日