大原雄介のカーエレWatch
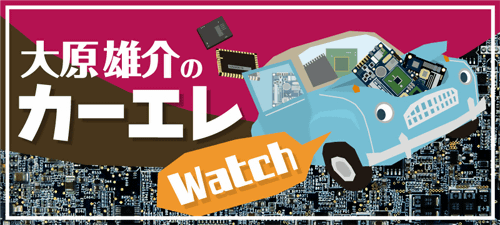
Active Safety(4)
2013年2月6日 00:00
前回はフェーズドアレイの手前までご紹介したので、今回はフェーズドアレイの話をメインに。日本語だと「位相配列」なんて呼び方をするが、あんまり一般的ではない。フェーズドアレイは一般にレーダーに使われることが多く、なのでPhased Array Radarの頭文字を取ってPARと呼ばれる事も多い。
さて基本的な動作原理である。とりあえず分かりやすいということで送信のケースを例にとってみよう。例えば図1の左のように、A~Cの3つのアンテナを並べて、電波を一斉に出すと、それぞれのアンテナから電波は均一に広がってゆく形になる。
ここで、AとB、AとC、BとC、それぞれの電波の重なりあう部分は特に信号が強まることになるのだが、この重なり合う場所は、アンテナに対して垂直方向に展開してゆくことになる。要するに、アンテナを横に並べて電波を送り出すと、真っ直ぐの方向に強い指向性を持つ電波という形になるわけだ。これはまぁ直感的に理解できるかと思う。
さて、図1では、A~Cの電波は全て位相を揃えた場合の話だ。位相が揃う、というのは図1の右側のように、3つの電波の山の位置と谷の位置がきっちり揃ったケースを指す。では、この位相をずらすとどうなるだろう? というのが図2である。
図2の右側に示すとおり、Aから出る電波と比較してB/Cから出る電波を、やや時間的にずらしたケースを考える。こうしたケースは「位相がずれている」と呼ぶのだが、するとA~Cから出る電波の山の位置が揃わないので、図2左側のように電波を強めあう方向性は垂直からやや右にずれた方向になる。要するにアンテナから出る電波の位相を細かくずらしてやることで、全体としての電波の向かう方向の角度を変えられる、というのがこのPARの基本原理である。
ちなみにこれはかなり端折った説明で、実際にはホイヘンス=フレネルの原理という波動の伝播に関する仕組みが根底にあるのだが、物理学の講義ではないのでこのあたりは割愛させていただく。
ちなみに受信側はどうするか?といえば、A~Cのアンテナがそれぞれ受信したものを重ね合わせるわけだが、この際にまったく位相差をつけずに重ね合わせれば、自分のアンテナと垂直方向の信号を受信することになるし、A~Cの電波に適当な位相差をつけて重ね合わせれば、図2のように斜め方向からの信号を受信する事になるわけだ。
これの何が嬉しいか、というのは前回の話に絡む。前回の説明の中で、複数の物体を感知するためには、アンテナを物理的に振り回すしかないという話をご紹介したが、PARの仕組みを使うとアンテナを物理的に振り回さなくても電波の進む方向を変えられるわけで、これは非常にメリットが大きい。
実のところ、このフェーズドアレイの原理そのものは昔から知られており、1905年には実証実験も行われている。また第2次世界大戦においては、イギリスとドイツの両方が、この原理を利用したレーダーの試作を行っている。にも関わらず実用化に至らなかったのは、やはり難しいからである。レーダーの周波数にもよるのだが、例えば第2次世界大戦当時で言えばMF(数百~数千kHz)~VHF(数十MHz)あたりの電波を使うことが多かった。周波数が低いほど長距離まで届きやすい一方、アンテナが大型化する(波長の長さに比例する)とか、回折現象により正確さに欠けるなどの問題もあり、次第に利用される周波数は上がる傾向にある。
まぁそれはさておき、例えば1MHzの電波を利用するとしよう。この場合信号1波長分の周期は
1÷1MHz=1μs
となる。
さて、フェーズドアレイで十分な精度を持ってある方向の送受信をしようと思った場合、(もちろんこれは規模とか要求される精度にもよるのだが)1/10波長程度の分解能では不十分で、1/100波長程度の分解能が必要というのが一般的な話になっている。で、1波長分の周期が1μsということは、分解能が100nsでは不足で、10ns単位での制御が必要という計算になる。
第2次世界大戦当時で10nsの分解能というのはかなり困難というか、現実問題として不可能に近い。先にもちょっと触れたがドイツは早期警戒レーダーとして「FuMG 41/42 Mammut」という巨大(ドイツ空軍用のものは30×16mというサイズであった)なPARを1944年に建設したものの、実際に運用されることはなかった。
利用される周波数は146MHzとさらに上だから、要求される分解能はさらに厳しいことになる。当時のことだから真空管ベースであり、当然ながらこんなスイッチング速度は出ないから、勢い精度が甘くなる。これは観測結果の誤差が猛烈に増えるということであり、実用に耐えなかったのも無理ない話である。
このPARが実用化されるのはもっと後になってからである。一番広く知られているのは、米海軍が1983年から運用を開始した「AN/SPY-1」というPARであろう。これは「イージスシステム」という名前で知られている火器管制装置の一部をなす「アレ」である。軍事用ということであれば、ある程度コストを度外視してでも高性能なシステムを作り込むことが可能であり、そんなわけで実用になったという次第だ。
そして1度システムができると、あとは技術の進歩などによりどんどん高性能化・低価格化が進むのは世の常である。初期のイージスシステムの場合、システム全体でおおよそ500億円程度と言われていた。このうちAN/SPY-1の価格がどの程度かは公開されていないから推測するしかないが、おおよそ数十億円のオーダーであることは想像できる。勿論最大500kmもの捜索範囲を持ち、平均信号出力64kW、同時追尾目標数200以上という化け物と自動車用レーダーを比較するのは間違っているのだが、例えば2010年になるとこれが手のひらに乗るサイズまで小型化されている。この記事にある富士通テンのレーダーモジュールの値段は不明だが、OEM向けということを勘案すればこの時期でも十数万~二十数万円のオーダーに収まっていたと思われる。現在は多くの会社が、この自動車向けのPARモジュールを高くても十万円台前半、安いものは十万をぎりぎり切る位の価格で提供しようと努力している真っ最中である。
どうしてこれが可能になったのか、といえばやはり半導体技術の猛烈な進化である。もともとレーダーで広く利用されており、今も一部の用途で使われているのは真空管である。よく利用されていたのはTWT(進行波管)で、大出力(数kW~数十kW)を小型・高効率で実現しようとすると、なかなか他に代わる素材がない。もっとも小型といっても重量は10kg以上、長さ50cm以上とかいうレベルで、これは基地局とか大型艦船に搭載するのは問題ないが、航空機やまして車に搭載するのはちょっと非現実的である。
ただ幸いに自動車向けはそもそももっと出力が低くてよい。こうした用途に利用されるのが1962年に発明されたガン・ダイオードと呼ばれるもので、構造が簡単で広い周波数で利用できるということで、現在も広く利用されている。実際、初期の自動車用レーダーはこのガン・ダイオードを利用したものが少なくない。
ガン・ダイオードの素子としてはGaAs(ガリウム砒素)を使うのが普通である。このGaAsを使うと比較的現実的な価格で自動車用レーダーを作ることは可能だったが、ただ自動車用PARというレベルまで持ってゆくのはちょっと難しく、アクチュエータを使って機械的に方向を変えたり、予め複数の方向に固定したアンテナを切り替えながら走査を行ったり、というレベルでしかなかった。これが大体2000年頃の話である。
では現在は? というと、ここからさらに一段進化した「MMIC」(Monolithic Microwave Integrated Circuit:モノリシックマイクロ波集積回路)を使うケースがほとんどである。日本語訳が日本語になってないのはこの世界ではよくあることである。MMICとは要するに、レーダーなどの高周波信号用の部品に、その周辺で必要となる回路までまとめて、それを小さなICにまとめてしまったものである。
一例としてPhoto02に示すのは、2003年に三菱電機が発表した、自動車向けレーダー用の送受信MMICである。米粒と比較すればその小ささがお分かりいただけるだろうか。ここまで小さければ自動車向けの搭載は比較的容易だし、コスト的にも十分競争力を持てるレベルになる。
加えて言えば、2000年というとPC向けのCPUがやっと1GHzの動作周波数になった頃。レーダーなどの組み込み機器向けは、まだ100MHz程度の動作周波数でしかなかった。ところが昨今は組み込み向けのCPUであっても1GHzを超えるものは珍しくなく、かつFPGAとかDSPといった、レーダー信号の処理に非常に適したデバイスがあるため、2000年当時と比較した場合、レーダー信号の処理能力は数十倍に増えている。こうなると、PARの実現に必要となる、位相差の生成・検出といった処理はデジタル回路を用いて容易に行えるようになっている。
こうした半導体の進化によって、従来は到底不可能と思われたPARを自動車向けに可能なサイズと価格に押さえ込んだことで、Active Safetyを実現するための手段の1つとして現実的に考慮される選択肢になってきたのが昨今の状況、というわけだ。
