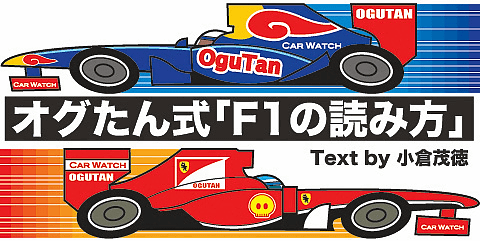 |
王者たちの王者らしい戦いぶり
 |
11月のF1は、アブダビ、アメリカ、ブラジルと、シーズンを締めくくる戦いとなり、チャンピオン経験者たちがグランプリドライバーらしいハイレベルな戦いを繰り広げてくれた。
日本GPでのリタイヤによって、チャンピオン争いでかなり不利に陥ったアロンソだったが、以後すべてのレースで表彰台に上がり、最終戦までチャンピオンへの望みをつないだ。だが、最終戦も2位でフィニッシュしたものの、セバスチャン・ベッテルの6位によってチャンピオンの夢は消えた。
フェラーリは最後までマシンのアップデートを行ったが、やはりレッドブルの速さと開発ペースにはかなわなかった。それでも、アロンソの最後まで諦めない姿勢はみごとだった。実際、最終戦の序盤では、王座獲得のチャンスがアロンソの手中におさまりそうなところまでいた。チャンピオンを獲得するのに必要なチームの総合力の向上、ドライバー自身の精神的な強さ、それにフェアな戦い方。アロンソはランキング2位に終わったとは言え、チャンピオンを目指す若手ドライバーたちにお手本となる戦いと走りをしてくれた。とくに、雨量が絶えず変化して難しいコンディションとなった最終戦での巧みな走りと戦いぶりは、アロンソが現代のF1を代表するドライバーであることを示していた。
 |  |  |
| フェラーリは最後までマシンのアップデートを行ったが、やはりレッドブルの速さと開発ペースにはかなわなかった | ||
ベッテルもまたみごとだった。終盤、速さと強さを取り戻したレッドブルRB8を駆って、シンガポールからインドまで4連続優勝。これで優位に立つと、表彰台を確保してその優位性を保ち続けた。最終戦ではスタート直後に追突されて最後尾に落ちながらも、自らの走りと実力で6位まで挽回。3年連続チャンピオンを獲得した。最終戦でただ速さを見せつけるのではなく、きちんとポイント差を考えた戦いもしていた。これは、今後のベッテルにとってもより強いチャンピオンとなるきっかけになったように思えた。
ランキング3位となったのは、今季F1に復帰したキミ・ライコネン。その戦いも素晴らしく、とくにアブダビGPでの復帰後初優勝は「ロータス」と名のつくチームで言えば、1987年のデトロイトGPでのアイルトン・セナによるキャメル・ロータス99T・ホンダ以来という歴史的なものでもあった。
 |  |
 |  |
| シンガポールからインドまで4連続優勝したベッテルは、3年連続チャンピオンを獲得した | |
ライコネンはこの勝利に向かう途中、セーフティカーラップ中にピットからの無線指示に対して「分かっているから、ほっといてくれ!」と返信。これもまた心に残るものだった。10年以上も前に自作PC誌「DOS/V POWER REPORT」のためにF1のテレメトリーを取材した段階で、そのテレメトリーのデータ量とチャンネル数、通信速度は、人類を初めて月に送ったアポロ11号のテレメトリーを凌いでいた。現代のF1も宇宙飛行のように、タイヤやブレーキの温度、エンジンの状態などさまざまなデータがテレメトリーによってピットにリアルタイムで伝えられ、そのデーターを元にピットのエンジニアが判断し、無線で色々とドライバーに指示や確認事項を伝えている。
トム・ウルフのドキュメンタリー小説に、「ザ・ライト・スタッフ」という初期のアメリカの宇宙飛行士とNASAの宇宙開発を題材にした作品がある(これは映画にもなった)。このなかで、宇宙飛行士たちは地上の指令センターからの無線指示という、管理された環境下で従順に作業することを求められる。だが、人類で初めて公式に音速を超えたチャック・イエーガーは、そうした宇宙飛行士への要求に反発。自分の技で飛行機を飛ばすとしてテストパイロットにとどまり、宇宙飛行士たちとは異なる道を選んだことも描かれていた。
現代のF1も、かつての宇宙飛行士たちのように、ピットのエンジニアからの無線指令に柔順になりがちなことが多い。だが、それは管理されている人を見ているようで、あまり面白くないこともある。
人間にはミスや見落としがあることを考えれば、もちろん確認事項など必要な無線連絡もある。だが、ライコネンが件の無線を返信した時点で、それは「すべてはオレに任せておけ!」ということでもあった。つまり、チーム、エンジンメーカー、スポンサーすべての期待と責任をすべて背負ってでも、自分の力でマシンを勝利に向かって走らせるという決意宣言でもあった。ここにライコネンの強さと自信が完全復活したように見えた。
アブダビでのライコネンには、かつての多くのF1チャンピオンがそうであったように、最後は自分の力で勝利を勝ち取るというヒーローの姿があった。ライコネンがモナコGPで1976年のチャンピオンであるジェームズ・ハントのヘルメットにしたのも、なんとなく分かる気がした。やはり自動車レースのドライバーは、イエーガーが求めたパイロットの姿勢と同様、自らの実力で戦う姿の方が素晴らしい。自動車レースの主役は、エンジニアではなくドライバーだということをライコネンは鮮烈に“魅せて”くれた。
マクラーレンの2人も終盤にきて速さと強さを取り戻した。ルイス・ハミルトンはアメリカGPで優勝。ブラジルGPでもニコ・ヒュルケンベルグに当てられてリタイヤしたものの、終始トップ争いをしていた。ドライバーが移籍を決めた時、自分の速さと強さをより示したくなるということを聞いたことがある。ハミルトンもまた終盤の好走で、これまで育ててくれたマクラーレンへよい置き土産ができ、来年加入するメルセデスには大いに期待されるだろう。
ジェンソン・バトンも最終戦で優勝。雨量が刻々と変化する極めて難しいコンディションのなかで、安定した走りとよりよい状況判断をし、バトン組の真骨頂を見せてくれた。シーズン途中で、タイヤの発熱に苦しんだこともあったが、やはりバトンの繊細なマシンコントロールの巧さが光っていた。
 |  |  |
| マクラーレンの2人も終盤にきて速さと強さを取り戻した | ||
ミハエル・シューマッハは、復帰後優勝できないまま現役を去ることになった。だが、随所でみごとな走りをみせてくれた。とくに、最終戦でのライコネンとのバトルは、お互いのタイヤがサイドポンツーンギリギリのところまで接近するサイド・バイ・サイドのままコーナーに進入。ギリギリのところで互いのラインをきちんと尊重しながらのバトルは、本当にハイレベルな戦いだった。
かつては、勝利のためなら相手を押しだしたりぶつけたりもしたシューマッハだったが、現役最後のバトルはとてもクリーンで、フェアで、スポーツマンシップとグランプリ王者としての風格のあるものだった。このシーンは、1979年フランスGPでのジル・ビルヌーブ(フェラーリ)対ルネ・アルヌー(ルノー)の白熱のバトルと同様に、今後も記憶に残るだろう。そして、粗いレースが目立った若手ドライバーたちへの模範にもなるだろう。
 |  |  |
| ミハエル・シューマッハは復帰後優勝できないまま現役を去ることになったが、随所でみごとな走りをみせてくれた | ||
■ベッテル対アロンソの傍らで
最終戦でのベッテル対アロンソの戦いの傍らで、そのチームメイトであるマーク・ウェバーとフェリペ・マッサもよい働きをしていた。互いに、チームメイトがチャンピオンを獲得するには自分がより高い順位でゴールして、ライバルの獲得点数を減らさせることが重要な状況だった。
「ベッテルを支援する気はない」と言っていたウェバーだったが、途中アロンソとバトルを展開した。また、ベッテルが低迷した序盤にはできる限り上位でゴールしようとする攻めた走りがみえた。
マッサは中盤にはベッテルを抜き、最後は2位の座をあっさりとアロンソに譲り、最善の仕事をした。マッサの走りは難しいコンディションでも力強く情熱が伝わってくるもので、速いマッサの復活を感じさせるものだった。
ニコ・ヒュルケンベルグも最終戦でトップを走った。しかも、ハミルトンを相手のバトルも展開した。最後は、濡れた路面でのブレーキングでマシンが滑り、ハミルトンに接触。ハミルトンをリタイヤさせて、ペナルティを受けてしまうという結果になってしまった。だが、ウェットコンディション絡みだったとは言え、フォースインディアのマシンでトップを争ったのは、その才能が非凡であることを示してくれた。
小林可夢偉もまた素晴らしい走りと戦いをみせてくれた。14番手スタートながら序盤の混乱を避け、中盤にはチャンピオンたちとのバトルを征して4番手に浮上。最後は遅すぎたピットストップのタイミングと作業で順位を落としたうえ、シューマッハとのバトルでリヤを滑らしてしまったが9位に入賞。シューマッハとのバトルでは、イン側の濡れた路面で滑ってしまったが、それまでの戦いもまた印象深いもので、小林の強さと実力の高さをはっきりと示していた。
 |  |
| 最終戦でのベッテル対アロンソの戦いの傍らで、チームメイトであるマーク・ウェバーとフェリペ・マッサもよい働きをしていた | |
 |
| 小林可夢偉の来季の動向に注目が集まる |
■小林可夢偉の未来とF1の内包する問題点
最終戦での小林について、ブラジルのテレビでは昨年までF1ドライバーだったルーベンス・バリチェロが高く評価するコメントをしていたと言う。それは、小林は安定感がある走りができ、しかも勝負どころで思い切りのよいオーバーテイクもできる優れたショーマンでもあるというもの。さらにバリチェロは、小林のような高い実力を備えたドライバーが来季の参戦が決まらないというのはおかしいと語っていたと言う。
小林への高い評価はそれだけではない。日本GP前にセルヒオ・ペレスが来季マクラーレンへの加入を発表したが、そこで英国の専門誌Autosportでは「マクラーレンは間違ったドライバーを獲ってしまったのではないか?」というコラムを掲載した。ペレスと小林の今季のレース内容などをもとに比較し、小林の方が安定していて、よりよい選択だったのではないかとしていたのだ。
だが現実は厳しく、ザウバーチームは来季ヒュルケンベルグに加えてエステバン・グティエレスをレースドライバーに、サードドライバーにはフォーミュラ・ルノー3.5チャンピオンのロビン・フラインスを起用すると発表。小林が来季のシートをどこかに獲得する前に、ザウバーが残留の選択肢がないことを先にはっきりと示してしまった。これは小林にとって、今後の交渉のなかで交渉のカードを奪われることになった。
それでも本来なら、今季9回の入賞を果たし、そのうち1回は日本GPでのマクラーレンのバトンとの真っ向勝負に勝っての3位という結果もある小林なら、他チームから契約金を積まれて三顧の礼で迎えられてもよい立場なはず。
 |
小林が直面している現実に、現在のF1が抱える問題点が浮き彫りになっている。
F1は極めて高コストなスポーツになっている。ミナルディが2005年に、スーパーアグリF1が2008年でF1から去ったときも、ともに年間30億円の活動資金ではただ参戦しているだけで、何も向上できない状況だとしていた。そして、トップ争いをするには年間数百億円の活動資金を必要とするとされていた。30億円とは、1990年代初頭のトップチームの年間参戦費用に相当する数値であり、F1の年間参戦費用はこの20年間で10倍以上になってしまった。
この状況に警鐘を鳴らしたのが、FIAのマックス・モズレー前会長だった。そして、2009年には翌年からの年間予算上限案を導入しようとしたが、大部分のチームがこれに反発して現在に至ったことも、8月の連載で書いたとおり。
2009年当時にヨーロッパ各国の経済状況を見れば、今日の信用不安とそれに伴う景気後退は分かったはず。主要チームの先見性のない我田引水な行動によって、現在の状況となっている。
結果、“プロフェッショナルドライバー”と言えるチームから契約金をもらって走る立場のドライバーは10人に満たないくらいとなり、あとのドライバーは何がしかの持参金が要求される状況になってしまった。そして、実力のあるドライバーが経験や実力は乏しいけれど、多額の持参金を持つドライバーに代わってしまうという状況に陥りがちになっている。これが、小林のような高い実力のあるドライバーがシート探しに苦労し、ヘイキ・コバライネンのように優勝経験があるドライバーが来年のF1残留に対して悲観的にならざるを得ない状況を作り出している。
 |
こうした実力のあるドライバーが減って、世界最高峰のドライバーを決めるレースと言えるだろうか?
HRTチームでは、最終戦の終了とともに大部分のスタッフは行き場を失ったという連絡がきた。スペインのチームとして旗揚げしたものの、スペインの景気後退でスポンサーがつかず、他国からスポンサーを獲得しようとしても「スペインのチーム」という点が災いしていた。HRTのケースは、「スペインの」というところを「日本の」に置き換えれば、かつてのスーパーアグリF1によく似ている。今回のHRTチームのなかには、スーパーアグリF1のメンバーだった者もいて、またしても同じような悲哀を味わっていると言う。
毎回マシンを改良し、最後までしのぎを削る面もF1の魅力ではある。だが、世界的に景気が後退しているなかでは、それにも限度が必要ではないだろうか。
F1世界選手権の歴史を振り返ると、1952年と1953年はF1マシンの必要台数を確保できず、F2マシンで戦った時代もあった。厳しい時にはGP2マシンかGP2のちょっと高性能版で凌ぐことも必要かもしれない。もしそうなっても、最高峰のドライバー達が今年の最終戦のようなみごとな戦いを繰り広げれば、何とか凌げるかもしれないと考えさせられた。
 |
| アメリカGPと同じ週末に行われた「第59回マカオGP」(写真は昨年のもの) |
■伝統のマカオGPで見えた日本の課題
アメリカGPと同じ週末に、「第59回マカオGP」が開催された。今年はグランプリのメインレースがF3になって30年目であり、またF3マシンが新規定となった初年度でもあった。
今年もイギリス、ユーロ、全日本、ドイツATSといった各F3シリーズのチャンピオンと上位勢がそろった。そして、GP2、フォーミュラ・ルノー3.5に進級したドライバーたちも一部戻ってきていた。
レースはとても手堅い展開となった。その理由は、今年から新たなマシンとなり、マシンを完全に使いこなせておらず、そのセットアップに大きな差が見られなかったのもある。また、ドライバーが賢くなり、頑張り過ぎてクラッシュするよりも、堅実に結果を出そうとする傾向も見えた。
そうしたなかで、レッドブル育成ドライバーで、今回フォーミュラ・ルノー3.5から戻ってきて終始速さを見せたアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが圧勝した。ただ、ダ・コスタ以外にも光る走りをしたドライバーもいて、来年の各F3、GP3、フォーミュラ・ルノー3.5、GP2が楽しみとなった。
一方、日本勢は、最上位が山内英輝の14位で、中山雄一が21位、平川亮はリタイヤに終わった。ここに日本勢の課題が見えた。
ヨーロッパ勢は、今年の新型マシンであるダラーラF312で1万km~1万5000kmは走っていた。だが、日本勢はレース開催数とテスト制限の関係から、ヨーロッパ勢の半分くらいの距離しか走り込めていなかった。しかも、優勝したダ・コスタの所属したカーリンチームは、フォーテックチームとともにマカオGP前週にもシルバーストーンでテストを行って、より慣熟度を上げてきていた。
日本のF3は、ドライバーもチームも本来ヨーロッパの上位チームと互角に戦える実力があった。それを取り戻すには、走行距離の差を埋めることが必要だろう。だが、レース開催数やテスト回数を増やすことは、そのままコスト上昇につながる。コストが上昇すればドライバーのシート獲得と参戦はより難しくなってしまう。
質的向上と競争力の向上。それに立ちはだかるコストとスポンサー獲得の問題。卵が先かニワトリが先かのような問題だが、日本のF3の高いステイタスを維持するには、どこかで課題解決のための糸口を見つける努力が大事だということも思い知らされた。
 |
| KV-1クラスで優勝した今市工業高校Aチーム |
■Ene-1 GP MOTEGI
一方、日本のモータースポーツと技術の未来に希望を抱かせるイベントが、ツインリンクもてぎで開催された。そのイベントとは「Ene-1 GP MOTEGI」のことで、鈴鹿で昨年から開催されているEne-1 GPのもてぎ版である。鈴鹿のイベントについては8月の連載で紹介したとおり。
もてぎ大会も車両規定は同じだが、コースが異なる。鈴鹿は多彩なコーナーと30mを超える激しいアップダウンのあるコースを走り、ハンドリング性能とエネルギー効率のよさによる耐久性が求められた。一方、ツインリンクもてぎ大会は、ほぼ平坦なオーバルコースを利用した1周のタイムアタックと60分耐久の走行となり、耐久性とともにスピードも求められた。そして、このスピードが大きな落とし穴になった。鈴鹿での上位勢がタイムアタックで速さを見せたものの、それによる電池消費がたたって60分の耐久走行で途中ストップしてしまう車両が出てしまった。
結果、最低重量無制限でより車体を造りこめるKV-1クラス総合では、今市工業高校Aチームが優勝。最低重量制限があり、車体をより安価に作れて参戦枠を中学生まで広げたKV-2クラス総合は、鈴鹿大会でもクラス優勝した飯田工業高校原動機部Bチームが優勝。高校生チームが一般や高専、大学生のチームを破った。飯田工業高校は、学校の統合によってこの校名が今年度いっぱいでなくなるため、母校に最後の栄誉をもたらした。また、鈴鹿大会でも活躍した信州大学付属長野中学技術部技術研究班チームがKV-2クラス4位と善戦した。
鈴鹿、ツインリンクもてぎのオーバルと異なるコースでの大会となり、このEne-1 GPは新たな魅力と技術的チャレンジのし甲斐が増した。そして、参加チームも地域的に広がりをみせている。
Ene-1 GPのKV-1とKV-2は充電池とモーターで走るエコランカーのような車両だが、それは電気自動車(EV)の基礎技術だけでなく、軽量で効率のよいクルマ造りの実践教育の材料にもなっている。それに中・高校生が積極的に参加しているのを見ると、彼等の将来も、日本の技術・産業の未来も頼もしく思えた。
余談だが、もてぎのオーバルを走るEne-1 GPマシンの速度は、1周のタイムアタックの最高平均速度で58.85km/hと、エコランカーを凌いでいた。また、このEne-1 GPにはコンバートEVによる競技部門もあり、ツインリンクもてぎ大会でも開催された。同部門では、N360をEVにコンバートしたホンダ学園自動車整備部が優勝した。
 |
| 盛大で豪華だった「Japan Lotus Day 2012」(写真は昨年のもの) |
■ヒストリックイベントも
11月は秋晴れのもと、ヒストリックイベントも多数開催された。なかでも、11月3日に富士スピードウェイで開催されたエルシーアイ(LCI)による「Japan Lotus Day 2012」はとても盛大で豪華だった。
このイベントは、歴代から最新のロータスが一同に会するもので、ピットガレージ、パドック、駐車場がさまざまな歴代ロータスで埋まる。今年は以下の10台のロータスF1が集まり、ロータス49を除く9台が走行した。
・ロータス49(1967)
・ロータス72C(1970)
・ロータス72E(1973)
・ロータス78(1977)
・ロータス78(1977)
・ロータス79B(1979)
・ロータス88B(1981)
・ロータス97T(1985)
・ロータス101(1989)
・ロータス101(1989)
これだけの台数のロータスF1が集まり、走行をしたのは日本初だった。
このF1の走行と展示は、日本のClassic Team Lotus Japanと英国のClassic Team Lotusとの協力で実現したもので、英国からはロータスの創業者コリン・チャップマンの長男でClassic Team Lotusの代表であるクライブ・チャップマン氏と、元ロータスF1チームメカニックで現Classic Team Lotus のマネージャーであるクリス・ディネージ氏も参加。また、マリオ・アンドレッティがチャンピオンを獲得した1978年からキャメル・ロータス・ホンダ時代まで、長年チーム・ロータスのタイヤ担当を務めたケニー・シュマンスキー氏もアメリカから駆け付けた。
走行後には、このロータスメンバーによるトークショーも行われ、貴重な歴史的証言を聞くことができた。また併催されたコンクールデレガンスでは、クライブ・チャップマン氏によって父コリンがロータス7の基本設計をわずか一晩で仕上げたというエピソードも披露してくれた。
秋の富士のストレートや100R、ヘアピンに響くコスワースDFVの音は、1976年と1977年にそこで開催されたF1を思い出させ、歴代のロータスのロードカーとともに夢のような1日となった。当日の詳しい様子や車両などについては、Classic Team Lotus JapanのWebサイト(http://www.classicteamlotus.jp/user_data/japan_lotus_day_2012_fsw.php)をご覧いただきたい。
レーシングカーとクルマとそれにかかわった人々は、その現役時代の活躍はもちろん、時代を経てもさまざまな魅力を伝えてくれる。ヒストリックイベントは、比較的安価な入場券で車両をそばで観られるものが多く、おすすめだ。
また、これからオフシーズンに入り、レースもヒストリックイベントも少なくなってしまうが、そんなときには自動車の博物館を巡ってみるのもよいかもしれない。きっと色々な発見があり、色々な思い出も蘇ってくるはず。そんな楽しみ方もよいかも。
■URL
FIA(英文)
http://www.fia.com/
The Official Formula 1 Website(F1公式サイト、英文)
http://www.formula1.com/
■バックナンバー
http://car.watch.impress.co.jp/docs/series/f1_ogutan/
(Text:小倉茂徳)
2012年 11月 30日