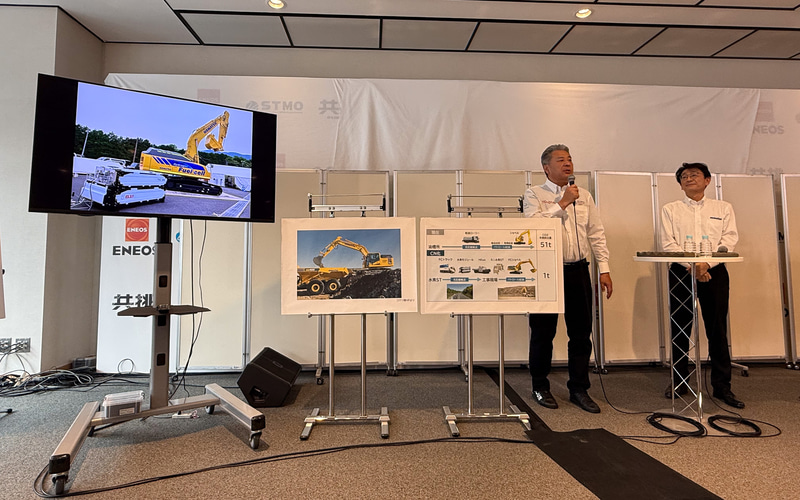ニュース
コマツ草場泰介CTOとトヨタ中嶋裕樹CTO、水素燃料電池搭載「中型油圧ショベルのコンセプトマシン」を解説
2025年6月1日 11:39
小松製作所とトヨタ自動車は5月30日、富士24時間レースを開催中の富士スピードウェイにおいて、コマツとトヨタが共同開発している水素燃料電池搭載「中型油圧ショベルのコンセプトマシン」に関する説明会を開催した。開発案件であるため、コマツからは草場泰介CTO(Chief Technology Officer)、トヨタからは中嶋裕樹CTOが参加し、報道陣からの質問にも答えた。
草場CTOは、中型油圧ショベルカーの開発の背景にはカーボンニュートラル化があるといい、この中型油圧ショベルのコンセプトマシンは20トンクラスのショベルカーであると語る。ショベルでは一度に0.8立米(立方メートル)をすくうことができ、最高速度は5.5km/h。働くクルマである建設機械の世界でもカーボンニュートラルの波は押し寄せており、新しい動力源が求められていたとのこと。そこに、トヨタが新型「MIRAI(ミライ)」に搭載し、実用化した水素燃料電池がマッチしたようだ。
もちろん、同様に動作時にカーボンニュートラルであるバッテリベースの建機も手がけており、「バッテリーで動く20トンクラスの油圧ショベルというのも弊社は持っていまして、すでにお客さまに使っていただいています。ですが、ほかのオプションとして、やはり水素、当然その先に同じようにアンモニアですとかエタノールですとか、いろいろなエネルギーがありますけど、そのすべてに関して幅広くやっていきたい」(草場CTO)と、さまざまなエネルギーによるカーボンニュートラルの取り組みを行なっている。
コマツが水素をエネルギーに使うのは、第一にカーボンニュートラル化のためだが、実際に実証実験をしている中でどのようなメリットが見えてきているのだろう。
草場CTOによると、実際に水素燃料電池を実装してよくなったことは音が静かになったこと。ディーゼルエンジンから水素燃料電池になることで圧倒的に静かになり、逆にほかの音が目立つようになったという。これはバッテリEVでも同様だが、音が出るエンジンがなくなり、タイヤや風邪切り音などほかの音が聞こえてくるといった現象が起きているという。
そして次に草場CTOが挙げたのは、排気ガスが出ないこと。当たり前だが化学反応で発電する水素燃料電池は、空気(酸素)と水素を反応させて電力を取り出し、水が生成される。そのため排ガスなどが出ず、限定エリアでの運用となる建機にとっても都合がよい。坑道など閉鎖空間での運用も考えられるが、それについてはバッテリ建機の運用を考えているとのこと。エネルギーミックスでの運用を考えている。
コスト面での質問も飛んだが、水素の長期的なコストはまだ見えておらず、実証実験で見極めようとしている。
コマツとしては、バッテリ車、燃料電池車、バイオ燃料、e-Fuel、水素混焼エンジン、水素専焼エンジンと多様なカーボンニュートラルに取り組んでいる。草場CTOは、その理由として自社のユーザーを挙げ、生産するためクルマを欲しているという。
そういった意味で、TCO(Total Cost of Ownership)が大切で、クルマを買って、運用して、そして売却してといったライフサイクルコストが事業に見合う形にならないと買っていただけないと建機ビジネスの一端を明かした。
具体的な数字の明言は避けたが、「正直に申し上げると、今の軽油で動いているクルマとほぼ同等までいかないと私は買っていただけないかなと思っています。その中には国だとか市だとか行政だとかが出してくださるインセンティブというのも、もしかしたら加わるかもしれません」(草場CTO)と語り、なんからの形で軽油並みの価格にならなければ、水素の本格普及にはならないとの見通しを示した。
そのほか、水素建機普及で大変なのは法律関連だという。水素は使うにおいて認可が必要で、工事現場で使うのに認可、それを地域移設するのに認可が必要とのこと。認可そのものはわるいことでないとしつつ、草場CTOは「このクルマをお客さんに買ってもらって使ってもらおうと思ったら、今、我々が経験したようなプロセスを経ないと使えないのかなっていうのは、大きな学びになります」と語り、今後水素が社会に普及し、手軽に使っていく上では、水素関連の認可に工夫が必要であるとした。