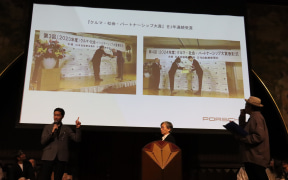ニュース
ポルシェ&東大独自の教育プログラム「ラーン ウィズ ポルシェ」に参加した学生たちは何を思う? 各界の著名ゲストも参加したシンポジウムを東大 安田講堂で開催
2025年2月18日 07:00
- 2025年2月16日 開催
ポルシェジャパンは2月16日、東京大学先端科学技術研究センター 個別最適な学び寄付研究部門と共同で実施している中高生を対象とした独自の教育プログラム「LEARN with Porsche(ラーン ウィズ ポルシェ)」の一環として、プログラムに参加したスカラーシップ生の学生たちが著名ゲストとディスカッションするシンポジウム「これからの教育探究会議『今の教育、これでいいのか?~中高生たちが審判を下す!~』」を東京大学 大講堂(安田講堂)で開催した。
当日はこれまでプログラムに参加したスカラー生の学生8人に加え、モータージャーナリストの藤島知子氏、音楽プロデューサー・作編曲家の松任谷正隆氏、スタートアップファクトリー代表の鈴木おさむ氏、料理研究家の土井善晴氏、ロボットクリエーターの高橋智隆氏といった各界の著名ゲストが多数参加した。
ラーン ウィズ ポルシェの活動を裁判形式でふり返り
シンポジウムの冒頭では、東京大学先端科学技術研究センター LEARNディレクター 中邑賢龍氏とポルシェジャパン 広報部 部長 黒岩真治氏の2人が登壇して、中邑氏がLEARNプログラムに込めてきた思いや黒岩部長が日本独自のCSR活動として2021年8月からラーン ウィズ ポルシェをスタートさせたきっかけなどを語るオープニングトークを実施。
この最後に中邑氏が「そんなわれわれの考えにもの申したいって言う人がいるんですよ」と水を傾け、鈴木おさむ氏が壇上に立つと、鈴木おさむ氏は「中邑氏が行なっているラーン ウィズ ポルシェの活動は子供たちを振りまわし、困らせている」と糾弾。
自らが検事を務め、中邑氏を被告と位置付ける「ラーン裁判」が開廷して、これまでラーン ウィズ ポルシェに参加したスカラー生8人は被害者、プログラムに協力した著名ゲストは参考人としてステージに上がり、会場に集まったシンポジウム参加者を陪審員とした法廷劇仕立てでラーン ウィズ ポルシェの活動についてふり返る「LEARNの教育を中高生はどう審判するか? -LEARN with Porscheの教育を受けた子どもにこの教育はどう映ったか?-」がスタートした。
鈴木おさむ氏は「ラーン ウィズ ポルシェでは『新しい教育』『突き抜けた教育』という名目で大人のわがままを押し付けているだけなのではないか」と疑問を呈すと、被告として証言台(演台)に立った中邑氏は「そうは言っても、それなら現代の一律一斉教育だけで日本はいいんでしょうか。そんな疑問点から(ラーン ウィズ ポルシェのプログラムを)始めました」と反論。鈴木おさむ氏はきれいごとだと受け流しつつ、スクリーンに過去のプログラムで撮影された写真を表示しながらスカラー生たちの活動内容を紹介して、中邑氏の“罪状”を挙げていった。
2021年8月に北海道で行なわれた第1回開催のふり返りでは、プログラムに協力した藤島知子氏と高橋智隆氏が参考人として証言を行なった。
藤島知子氏は「十勝スピードウェイ」でポルシェの「911 ターボ」と「タイカン ターボS」の助手席にスカラー生たちを座らせてサーキットの全開走行を体験させる役割を担ったが、鈴木おさむ氏は「さんざん不安にさせておいて、最後にポルシェに乗らせてテンションを上げて終わりにさせている。全開走行なんて危ない!」と糾弾。これに対して藤島知子氏は「クルマは公道では飛ばして走らせたらダメじゃないですか。でも、クルマって思い切り走らせると心をときめかせる何かがあるじゃないですか。ポルシェ 911の珠玉の走り、そして電気自動車であるタイカンの走りを、皆さんは本当に楽しそうに味わっていました」と反論した。
また、2023年8月に東京都~北海道で行なわれた第4回開催のふり返りでは、ポルシェジャパンの黒岩部長がスポーツカーメーカーであるポルシェがLEARNプログラムのパートナーになることで、スカラー生たちに最新・最良のポルシェモデルに触れてもらい、とくにこの回では礼文島まで911とタイカンをフェリーで運び、美しい山並みを背景に記念撮影。この1カットはドイツ本社でも高く評価され、ポルシェのCSR活動を紹介する素材として活用されているとアピール。
さらにラーン ウィズ ポルシェは日本国内でも評価されており、日本自動車会議所と日刊自動車新聞が主催する2024年度の「クルマ・社会・パートナーシップ大賞」で「SDGs貢献賞」を受賞。ポルシェジャパンは前年度にも「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」がある千葉県木更津市での活動が評価されて「地域・コミュニティ活性化賞」を獲得しており、2年連続での受賞はポルシェジャパンが初で、これはスカラー生たちが参加してくれたおかげだと感謝の言葉を口にした。
「60年代の空冷ポルシェを甦らせよ! -人や機械からものづくりの知恵を学ぶ5日間-」というタイトルで、工業高校や高等専門学校の学生を対象に実施された回のふり返りで、鈴木おさむ氏はブルーシートで覆った“古いポルシェ”にスカラー生たちは期待していたが、その下からは空冷2気筒エンジンを搭載したポルシェ製のディーゼルトラクターが姿を現わし、学生たちからは落胆の声が漏れたと表現。さらにレストア作業も手順などが学生たちに任され、多くの時間を浪費するシーンもあったと説明した。
参考人として証言した池田猛氏はトラクター修理歴40年以上というベテランエンジニアで、「私だって職についてすぐのころは、こんなことはできませんでした。先輩の作業を見たり、本を読んだりして少しずつ知識を広げてやっとできるようになったんです。誰も最初からはできないんですよ」とコメント。
また、中邑氏は「本当は彼らにはできるポテンシャルがあるんです。でも、そういう場所を作っていない。考えなくていい、早くやりなさいと、スムーズに早くやることがよいことになってしまっているから、一番大事なところがブラックボックス化されて、何も分からない」。
「世の中の子供たちは大人をなめていて、『インターネットもろくに使えない』『ATMの前で操作できなくなってる』と思っているけど、そのおじいちゃんおばあちゃんたちは実は凄いことをやってきた人たちなんだぞと、凄い大人を見せたいわけです。一方で、大人側でも自信を持って『かかってこい』と言える大人が増えないと、本当の意味でよい教育はできないんじゃないかと思ってやってるんです」とプログラムの意図を説明した。
ひととおりのふり返りが終わり、鈴木おさむ氏が「中邑被告が行なったことは『新しい教育』という名で子供たちを追い詰め、不安にさせて傷付けたものだ。大人の横暴なのではないか」と締めくくって陪審員による判決に移ろうとしたタイミングで、これまで裁判を静観していたスカラー生の学生たちが次々に手を挙げ、被害者の立場から中邑氏の弁護人に転身。ラーン ウィズ ポルシェのプログラムで得た学びや自分に起きた変化などを語り、検事の鈴木おさむ氏に異議を唱えていった。
「確かにラーンは横暴だと言えるかもしれません。しかし、そのようなスタンスではこれからの時代に対応できないと思います。現在、地球温暖化による気候変動やAIによる職業の代替など、私たちが住む時代はすでに予測不可能になっています。私たちの実生活はラーンより予測不可能かもしれません。それなのに、学校では受験向けの現実離れした知識ばかり詰め込み、実践的な経験を二の次にしています。これでは、この先をどのように生き抜けばよいかわかりません」。
「ラーンでは、学校ではできない体験を通して学び、自分たちの頭で考えて対処することを経験しました。これは今の教育の需要に則している非常に求められるプログラムだと思います。それに、このプログラムは理不尽に見えるかもしれませんが、今の学校教育にも違った形の理不尽があるかもしれません。私たちの社会は実に多様な人々で構成され、健常者のほかに障がい者の方や持病がある方、日本人のほかに海外にルーツがある方など、そのような人々は日常的にさまざまな理不尽を経験しています。それなのに、学校ではそういった人々の苦労をほとんど教えてくれません。これではSDGsや多様性と言っても名ばかりではないでしょうか」。
「このような学校教育で、本当に誰もが受け入れられる包括的な社会を実現できるのでしょうか。ラーンではさまざまな試練を設けて日ごろの生活では気付けないようなバリアに目を向けさせ、子供たちの視野を広げてくれる真に価値あるプログラムだと信じています」などと語られた。
そんなスカラー生たちの言葉を聞き、鈴木おさむ氏の「ラーン ウィズ ポルシェが子供たちにとって『新しい教育』だと思うか」という問いかけに対し、会場の席に座った陪審員は大多数が賛同の挙手をしてラーン裁判は判決となった。
最後に中邑氏は「よく『ラーンをやって効果はあるんですか?』と質問されることがあるんですが、そんなこと知ったこっちゃないと思っているんです。みんなに褒めてもらってうれしいけど、でもそれは今のことで、これが10年先、20年先にどうなっているかがもっと大事なことです。僕たちがよいことだと思っていることをみんなに提示して、その場を使うのは若者たちであり、それに『何を期待しているんですか?』『どうしたらいいんですか?』という問いかけには、そんなこと知ったこっちゃないんです。君らが考えて、その場を利用して、君らの将来に何か役に立てばいいけど、役に立たないかもしれないよと思いながら実はやっている、そういったプログラムです」。
「ひねくれた考えかもしれませんが、でもそんなふうにやっていかなければ教育なんてできない。先生や大人たちは『これはどんな効果があるんですか?』と問われると無理矢理何かしら効果を出そうとしてしまう。本当にうさんくさいコメントが世の中に出まわっている。そうじゃなく、子供たちみんなが自律的に『これはよい』『これをやっていこう』と思うようになったらそれに取り組んでいけばいい。それが一番大切なことなんじゃないかと僕は思っているところです」と締めくくっている。
著名ゲストが楽しんで続けられる秘訣と挫折を語る
ラーン ウィズ ポルシェのふり返り報告に続いては、「教育とは違う分野のリーダーたちがこれからの若者に何を望むか?」というテーマで参加した著名ゲストと中邑氏が対談する時間が用意されていたが、中邑氏が「説教臭い時間にはしたくない」との思いから急きょ内容を変更。それぞれの分野をリードする面々が、楽しんで続けることができた秘訣とあきらめて挫折した部分を若者たちに語ってもらうことになった。
中邑氏が「ロボちゃん」と呼んでいるというロボットクリエーターの高橋智隆氏は、ちょうど就職活動が始まる前にバブル経済の崩壊が起き、自分が入りたかった会社に落ちて挫折を実感。自分がもの作りの道に進みたかったのにエスカレーター式だからと文系の大学に進んだことを後悔して、そこから工学系の大学に入り直し、卒業と同時に自分の会社を設立。そこからロボットの研究を続けながら何十年かの歳月が経過して、挫折の原因になった会社の社外取締役に就任しているとコメント。普通のキャリア、普通の暮らしはあきらめることになったが、一方で行き当たりばったりながらも人とは違う、何をやっている人なのかわからない生き方を楽しんでいると説明した。
また、ラーン ウィズ ポルシェのプログラムでは使用禁止になるなど目の敵にされている感のあるスマートフォンだが、これからはスマホがロボットになり、「小さな相棒」になるのではないかとの将来予想を語り、これから先にスマホ自体、そしてスマホの先にある情報とどのように付き合っていくかを見極めていくことが重要になっていくと述べた。
音楽プロデューサー 作編曲家であり、日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務めている松任谷正隆氏は小学生のころ、まずい給食を食べたくなくて、とくに嫌いだったホワイトシチューが出る日は渋谷駅の駅長室に仮病を使って転がり込んでいたというエピソードを紹介。続く挫折は大学時代で、3年生になってそろそろ就職活動を始めようかと考えていたら、周囲から「今さら遅いぞ」と言われて現在の立場になったと淡々と語った。
これまでの活動については、遊びの延長としてこれまで続けてきたことばかりだとふり返り、仕事として考えていた時期もありつつ、今の年齢になるとやはり仕事じゃなかったと口にした。
また、新車から25年以上にわたって同じポルシェに乗り続けていることについて中邑氏から質問されて「自分が長く持ち続けている物に対する自分というか、向き合っていることで何かが見えてくるように感じます。それが何なのかはよくわかりませんが、自分の性格は見えてくる気がします。あと、ポルシェは1980年から持ってます。また新しいのがほしいなぁ」とコメントした。
料理研究家の土井善晴氏は、自分の将来を考えた際にフレンチから中華、和食まで料理と名のつくものはすべてできるようにならなければと考えて渡仏。プロの世界に飛び込んで三つ星レストランなどでも修業を重ね、フランスで日本料理店を開店して、パリで成功することで初めて日本の料理が世界に認められると意気込んでいたが、同じく料理研究家である父親の経営する料理学校が経営不振に陥り、日本に帰国するときに「日本一になりたい」「超一流になりたい」という夢を捨てることになったという。
父親の後を継いでテレビ番組などに出演するようになってから、家庭料理は儲けとは無縁な一方、それまで自分が追い求めていたプロの世界は全体から見るとほんの一部で、すそ野が広い家庭料理は自分がまだ知らないことばかりだと実感。上ばかり目指していた自分が視線を横に向けると、そこに自分がやるべき仕事があったと表現して、「美味しいものを作ろうと思わないところに美味しいものが生まれる」との考えに至ったと語った。
東京大学 先端科学技術研究センター 所長として再生可能エネルギー研究に従事している杉山正和教授は「勉強ができることが自分のアイデンティティだった」と語り、東京大学に入学してからは外の世界に出たことがなく、先ほどのふり返りで紹介されたラーン ウィズ ポルシェの「受験勉強だけが勉強じゃない」という考え方と真逆のような生き方をしてきたと自己紹介。
当時師事していた教授に誘われて東京大学で研究を続けることになったが、そのときになって「自分が研究したいテーマが何もない」ことに大いに悩んだという。テーマが定まらないことで目立つ成果も挙がらず、順調なステップで東京大学の研究者になったものの、直後から落ちこぼれ研究員の道を進み始めてしまった。
しかし、1972生まれの杉山教授は当時のオイルショックについて両親から話を聞かされ、とくに電力会社で働いていた父親から「おまえが大人になることには石油は枯渇している」と言われて「次のエネルギーを探さなきゃ」とスカラー生心に考えていたが、その後の受験勉強の忙しさですっかり忘れていたことを30代半ばになって思い出し、そこから再生可能エネルギーの研究に取り組むようになったと明かし、テーマが決まってからは研究したいことが出てくるようになったという。
カーボンニュートラルという言葉は難しく聞こえるものの、自分たち研究者が新しい何かを生み出して世界に広まれば、カーボンニュートラルが実現できるかもしれないという思いで研究を続けているが、土井善晴氏の言葉と同じように、「いい研究がしたい」「これは上手くいきそうだ」と狙って手を出すと外れてしまうので、どの世界も同じだと思いながら話を聞いていたと語った。
重要なのは最終的に自分のコアになる部分を見つけること
ポルシェジャパンの代表としてシンポジウムのクロージングで登壇したフィリップ・フォン・ヴィッツェンドルフ氏は自身も6人の子供がいる父親であると語り、紹介されたラーン ウィズ ポルシェのプログラムが非常に有意義なものだと評価。それはポルシェジャパンのため、LEARNプログラムのためといったものではなく、純粋に参加したスカラー生のためになっていると感じているからだと語った。
直前に行なわれた著名ゲストと中邑氏の対談の対談では、立場のある各ゲストが自分の挫折や失敗について口にしたことの「正直さ」、有名になっても心を開いて語る「謙虚さ」をこの場にいる若者たちに教訓としてほしいと説明。LEARNプログラムのディレクターである中邑氏と対面して、中邑氏が若者たちのことを最優先して、さまざまな経験の場を与え、ゴール設定や点数付けをせず自分たちで答えを見つけていくことが大切だと考えていることに共感してLEARNプログラムに協賛することを決断したと明かした。
また、登壇したスカラー生たちの言葉を聞き、スマホや教師、親でもなく、彼らが自分なりの道を見つけていることを実感したと賞賛。もちろん、スマホや教師、親を頼りにすることは問題なく、重要なのは最終的に自分のコアになる部分を見つけることで、これは人生で最も難しいタスクなのかもしれないが、自分がどんな人間か知ること、自分が何をしたいか、何ができるのかを見極めれば、できないことはないのだとエールを贈り、ラーン ウィズ ポルシェはまさにその大切なコアを見つけるプログラムが用意されていると評価。そして探し出して終わりではなく、年齢を重ねて老人になっても自分探しは常に続くものだと語った。
このほか、人生には何らかのゴールを設定することが重要で、野心的なゴールであり、単なる目標地点ではなく夢として抱くことで、そこから情熱が生まれてくると説明。夢にたどり着くまでは時間がかかることもあり、あきらめない粘り強さが大切だと若者たちにアドバイスした。