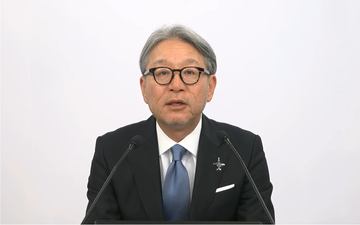ニュース
日産、2024年度 第3四半期決算 売上高0.3%減の9兆1432億円、営業利益86.6%減の640億1000万円、当期純利益98.4%減の51億4800万円
2025年2月14日 09:37
- 2025年2月13日 開催
日産自動車は2月13日、2024年度 第3四半期(2024年4月1日~12月31日)の決算を発表。オンラインに加え、神奈川県横浜市にあるグローバル本社で決算説明会を開催した。
2024年度 第3四半期の売上高は前年同期(9兆1714億600万円)から0.3%減となる9兆1432億700万円、営業利益は前年同期(4783億7500万円)から86.6%減の640億1000万円、営業利益率は0.7%、経常利益は前年同期(5401億2300万円)から70.5%減の1594億1700万円、当期純利益は前年同期(3253億5400万円)から98.4%減の51億4800万円。また、グローバル販売台数は前年同期(244万1000台)から4万4000台減の239万7000台となった。
また、決算に関連して、2024年12月に発表した本田技研工業との経営統合について、同日取締役会を開催。基本合意書を解約し、経営統合に関する協議・検討を終了することを決議して、両社間で合意。合わせて三菱自動車工業を含む3社での協業形態について検討する覚書についても解約することで合意したことも説明された。
「日産が持つポテンシャルを最大限引き出せると確信を持てなかった」
決算説明会で登壇した日産自動車 代表執行役社長 兼 CEO 内田誠氏は決算説明に先立ち、同日発表されたホンダとの経営統合に向けた協議打ち切りについて説明。
内田社長はホンダと立ち上げた「統合準備委員会」での議論により、初期段階の検討として大きなシナジー効果が期待できるとの手応えを得たものの、その後にホンダ側から基本合意書で合意した枠組みとは異なる「株式公開による日産の完全子会社化」という形態に変更したいとの提案を受けたと説明。
この真意として、内田社長はシナジー効果を得るために、統合を迅速かつ効率的に進める必要があるとホンダが判断したとの理解を示しつつ、日産社内での取締役会で慎重かつ真摯な審議を重ねた結果、最終的に日産の完全子会社化という提案には応じられないとの結論に至ったと述べた。
基本合意書を解約した最大の理由として、今回の経営統合は日産とホンダが力を合わせ、より強い企業体になることでグローバル競争に打ち勝っていくことを目指していたが、日産がホンダの子会社となった場合に「日産の自主性をどこまで守ることができるか」「日産が持つポテンシャルを本当に最大限引き出すことができるのか」という2点について確信を持てなかったことにあると解説した。
一方で今後については、両社の経営統合とは別に検討を進めている戦略的パートナーシップについては、新たな価値の創造と効率的なシナジー効果の実現を目指して協議を続けていくとアピールしている、
売上高0.3%減の9兆1432億円ながら営業利益86.6%減の640億1000万円で減収減益
決算内容については1月1日からCFO(最高財務責任者)に就任したジェレミー・パパン氏が説明。
パパンCFOはグローバル販売台数で、北米市場では対前年比2.4%増となったがその他の市場で販売台数を伸ばせず、とくに中国では引き続き厳しい状況が続いて全体で1.8%減という結果になったと述べた。
営業利益の増減要因としては、「為替変動」で314億円、「原材料費」で235億円の増益効果を得たものの、販売台数の減少と販売費用の増加、新型車の市場投入に向けたマーケティング投資などの要因があった「販売パフォーマンス」で2143億円の減益要因となったことに加え、「モノづくりコスト」で595億円、「インフレ影響」で1063億円、「その他」で892億円の減益要因が発生している。
これらについては日産固有の課題と厳しい市場競争が利益を圧迫しているが、一方で日産が進めているさまざまな取り組みにより改善の兆しも見えており、これから市場投入される、中東の「パトロール」「キックス」「インフィニティ QX80」、米国の「アルマーダ」といった新型車が販売を牽引して台数を伸ばしていくと解説した。
2024年度通期の純利益は800億円赤字の見通し
続いて2024年度通期の業績見通しについては、前回見通しから売上高を2000億円減の12兆5000億円、営業利益を300億円減の1200億円に下方修正。また、前回見通して未定としていた当期純利益については800億円の赤字となる見通しを示した。
売上高は卸売り台数の減少、販売費用の増加などの影響で、当期純利益は第4四半期中に確定する予定のリストラ費用として1000億円が計上されたものになる。なお、グローバル販売台数と生産台数については前回見通しの数値を維持している。
生産能力を2024年度の500万台から2026年度に400万台まで削減
パパンCFOによる通期見通しの説明に続き、内田社長から2024年11月に発表された「ターンアラウンド」の進捗状況について紹介された。
ターンアラウンドでは2026年度までに「年間350万台の販売でも持続的可能な収益性とキャッシュを確保できる体制」に会社を変革。戦略的パートナーシップを推進させて投資効率と商品競争力を高めていくことを目指し、この取り組みを迅速に進めるため、組織と経営体制を改革してプロセスの効率化を推進する取り組みを開始している。
まず事業体制では、持続的な収益と財務の柔軟性を確保するため、固定費で2024年度比で3000億円以上、変動費で1000億円以上を削減。固定費では組織のスリム化によるポジション削減、新規採用の抑制と早期退職制度の拡大で間接部門の人員をグローバルで2500人削減。さらに1000人分の業務についてシェアードサービスセンターに移管することでコストを削減する。合わせて全体的な経費削減も350億円規模で実施する。
マーケティング活動、スポンサーシップ活動にも優先順位を設定して投資効果の最大化を図り、広告宣伝の計画と購入戦略を改革して広告アプローチを抜本的に見直して固定費を削減する。
生産拠点の再編も行ない、拠点の適正化と再編を進めるため、車両工場、パワートレーン工場で2025年度に5300人、2026年度に1200人の人員削減を実施。2025年度第1四半期にタイ・第1工場、同第3四半期と2026年度に2工場を閉鎖することを計画しており、米国にあるスマーナ工場、キャントン工場で2025年度からシフト変更を行なって、工場ラインの最適化により470億円/年の固定費削減と400億円/年の変動費削減を見込んでいる。
このほか、新型車の生産準備におけるコスト最適化、新車投入に伴う設備投資とコスト削減も推し進め、生産部門で1000億円をコスト削減する。
グローバルでの生産能力は2024年度の500万台から2026年度には400万台まで削減。すでに実施済みとなっている中国における50万台分の規模縮小と前出の3工場の閉鎖などにより、工場稼働率は現状の70%から85%に上昇する予定となっている。
商品開発でもプロセスの効率化などによって300億円以上をコスト削減。新しい商品開発プロセスでは企画と開発の連携をさらに強化。デジタル開発による期間短縮とフィジカルでの試作ロット削減を推し進める。この新プロセスを適用する最初のモデルを2026年度に市場投入すること予定して進めており、また侵攻中のプロジェクトにも一部適用して、2025年度からコスト削減効果が表われてくるという。
具体的には、「メインモデル」では開発期間をこれまでの52か月から37か月に、「後続モデル」ではこれまでの50か月から30か月に短縮することになる。
変動費の1000億円削減に向けては「仕様の適正化」「製造コスト削減」という2つの手段を実施。
「仕様の適正化」では購入者に競争力ある価格で価値を提供するため、市場の基準に合わせて商品設計の見直しを行ないコストを最適化。これに向けて現在グローバルで展開している主要6車種に適用して600億円をコスト削減していく。
「製造コスト削減」では部品種類を70%削減し、生産計画の改善でサプライチェーンを効率化して保管費用を抑制していく。また、アフターセールス部品でも管理の効率化でコスト削減を進めていく。
第3世代e-POWERを欧州発売の「キャシュカイ」に搭載
将来的な成長に向けた商品ラインアップの強化では、まず2024年度に商品刷新、商品力強化などを行なった主要モデルについて解説。
日本市場で発売した「ノート」「ノート オーラ」のマイナーチェンジモデルがコンパクトカーセグメントでNo.1モデルとなり、米国では新型「キックス」が高い実用性とデザイン力によって好調なセールスを記録。フラグシップSUVであるインフィニティ QX80は先進技術とラグジュアリーさが評価されてグローバル市場で存在感を高めているとした。
中東では圧倒的なオフロード性能を誇る「パトロール」が支持を集めており、販売が好調に推移しているパトロールやインフィニティ QX80、「アルマーダ」といったSUVを生産している日産車体九州では増産体制の準備を進めているとアピールした。
こうした販売モメンタムを維持するために必要なニューモデルとしては、米国向けに「ローグ PHEV」「ローグ e-POWER」を展開。日本市場では新しい軽自動車や大型ミニバンの導入で商品ラインアップを強化していく。
BEV(バッテリ電気自動車)では新型「リーフ」をグローバルで販売し、さらに欧州市場にはコンパクトEVもラインアップに追加。中国向けとしてはNEV(新エネルギー車)である「N7」を2024年度中に発売される。
ラインアップ強化では、ルノー、三菱自動車、東風汽車などとのパートナーシップをフル活用して効率的な投入を進めていくとした。
日産の電動化戦略で柱の1つとなっているe-POWERでは、“第3世代システム”を2025年から欧州で販売する「キャシュカイ」に搭載予定。そこから米国のローグ、日本の大型ミニバンに順次展開していく予定だと明らかにした。
第3世代となるe-POWERでは、進化したe-POWER専用エンジンと電動パワートレーンの統合を行ない、燃費や静粛性をさらに大幅向上。コストについても大きく下げることができるという。また、長距離移動も多い海外市場で重視される高速燃費の面でも優れた性能を発揮するようになり、第1弾となるキャシュカイでは従来型から15%の燃費改善を実施してクラストップレベルの燃費を実現する見込みとした。
クルマの知能化にも引き続き注力。2026年までは「インテリジェントコックピット」と運転支援技術の進化に取り組み、2026年以降はドアトゥドアの自動運転技術やLiDAR技術による次世代の衝突回避機能などを実用化して普及を進め、さらに先ではドライバーレスのモビリティサービスを実用化して、安全で快適なモビリティ社会実現に貢献していくとロードマップを説明した。
車両販売については中国を除いて270万台を見込む2024年度から2026年には30万台増の300万台を目標としており、パートナーシップを活用する競争力の高い商品投入、中国からの輸出による販売機会の最大化などを含め、戦略的な検討を進めていると説明。
組織とプロセスの最適化では、役員体制をこの4月から大きく変更。現在の執行役員体制を廃止してCEOと各ファンクション、リージョンの責任者のみに改め、現在の執行役員を執行職としてポストを2割削減。各執行職の担当領域や責任範囲が広がってレイヤーがなくなることにより、意思決定と実行のスピードアップが図れる。また、若手の抜擢も促進して次世代リーダー層の育成、社内の活性化を推進していく。
グローバルとリージョンの役割分担も明確化。上流機能の権限を本社に集約し、顆粒機能をリージョン側に権限委譲。本社機能のスリム化を進めてオペレーションの効率を全体として向上させていく。
今後はターンアラウンドの実行スピードをさらに加速させて1日も早く成果を出していきたいと意気込みを語りつつ、一方で日産の足下のパフォーマンスや変化を続ける事業環境を踏まえた場合、あらゆる選択肢を聖域なく検討し、さらに踏み込んだ構造改革を進めていくことが不可欠になると分析。
そのために、事業とポートフォリオ(資産構成)でどのマーケットにどのように残り、どのような事業運営をしていくのかについてより明確化。商品やパワートレーン、プラットフォームについて優先順位を与え、残すもの、止めるものを仕分けていく。ルノー、三菱自動車とのアライアンスやホンダなどのパートナーと進めているプロジェクトは取り組みをさらに加速させていく。
現有資産の最適化では、コスト削減と効率性向上につながるあらゆる機会を明確化。事業の効率性を高めるため、事業のカーブアウトや資産の統合とリースバックなどの検討も進めていく。
一方、現状の事業環境ではここまでに紹介してきた施策だけで生き残っていくことは厳しいと考えており、すでにあるパートナーシップの効果を最大化していきつつ、ストラテジックレビュー(戦略検討)を行なって新しいパートナーシップの機会についても積極的に模索して企業価値の最大化を推進していくと説明した。
質疑応答
質疑応答ではホンダとの経営統合に関する協議終了について内田社長の受け止めについて質問され、内田社長は「一部の報道で『日産がプライドにこだわっているんじゃないか』とか『対等で』といった言葉も散見されていますが、当時のMOU(基本合意書)の時点で経営統合の持株会社はホンダさんが社長を出し、ダイレクターもホンダさんが過半を占めるということで、当社がポストとかわれわれのプライドといったものより、経営統合する会社が強くなることにかけていたという気持ちがあります」。
「そういった中で、経営統合をホールディング会社を建てて、そこに両社をぶら下げるという形態と、ホンダさんから提案された完全子会社化という形において、これは日産の意見ですが、非常に長い歴史のある中で、われわれを含めた一部自主性であったり、われわれの強みが発揮できるような形になるんだろうかと、ここが非常に悩んだ点です」。
「両社で未来を見据えて強い会社になりたいという思いは、私もそうですし、なんとかMOUをつうじて経営統合を成功させたいという気持ちは非常に強くありました。ただ、そういった中で今回のご提案というところにおいては、さまざまな論議をうちの経営層、ならびに取締役会でもいたしました。正直、当社が現在の経営状況で1社でやっていく難しさもありますし、そういった中で今回のご提案をどのように考えるか真摯に論議したということが経緯であります」。
「その中で、われわれが描いていた当初の経営統合のホールディング会社をもって、その会社を強くしていく。そこにいろいろなファンクションを置きながら、われわれが外に対して戦っていけるような形を取るということが日産としては一番望んでいた形で、今回はそういった形になれずに、同意が得られなかった。経営統合の方向としては非常に残念に思っています」。
「ただ、ホンダさんとは未来志向を見据えて、今進めているパートナーとしての協業に関しては、われわれもいろいろな提案をさせていただきながら両社にとっての未来志向を見据えたメリットになる形につなげていきたいと考えています」と答えた。
また、業績不振が続いている原因について問われ、内田社長は「さまざまな点があると思いますが、主要市場である北米でわれわれのコアモデルが計画どおりに台数が出なかった。また、計画どおりの販売支援金で販売することができなかったという点に尽きると思います。われわれのVME(可変マーケティング費用)が2024年度 第1四半期で上がったレベル、第2四半期と第3四半期では下げてきていますが、現在の競争状況を踏まえると、第4四半期でもそれなりのVMEを使わざるを得ないという点から今回の数値に陥ったということが背景にあると思っています」。
「合わせてコスト的な構造で見ると、われわれとサプライヤーさんとの関係の中で、かかるインフレコストは適正にやっていますが、当社が過去からあった台数に届かなくなって補償しなければいけない部分のコストもそうとうかさんでいることも事実としてあります」。
「重要なことは、われわれが社内で言っているカーフローと呼ぶ部分の適正化をさらに図り、生産変動が大きく振れない形を2025年からできる体制で進めることを踏まえ、今回の見通しの数字になっていることが大きな背景にあります」とコメントしている。