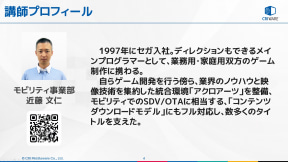トピック
「ソフトウェア・デファインド・バリュー」を目指すCRI・ミドルウェア 近藤文仁氏がゲームの理論でSDVを紐解く
2025年2月21日 07:00
- 2025年2月18日~20日 開催
SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)時代の自動車ソフトウェア開発とモビリティ社会のこれからを探るオンライン講演会「第10回 オートモーティブ・ソフトウェア・フロンティア 2025 オンライン」(主催:インプレス、共催:名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所)が2月18日~20日に開催された。
自動車メーカーや部品メーカー、ティア1、ティア2、OEM系ソフトウェアメーカー、半導体メーカー、組み込みソフトウェアメーカーなどで研究開発に携わるエンジニアを中心に、事前登録するだけでZoom/Vimeoから無料参加できるこのオンライン講演会では、SDVの概念が広く認識されるようになってきた昨今のソフトウェア開発の最前線で活躍する多彩な講演者が講演を実施。
開催2日目の2月19日にもさまざまな講演が行なわれたが、本記事ではCRI・ミドルウェア モビリティ事業部 副部長 近藤文仁氏によるソリューション講演「ゲームの理論でSDVを紐解いたら、世界はもっとシンプルだった件」で語られた内容について紹介する。
ソリューション講演「ゲームの理論でSDVを紐解いたら、世界はもっとシンプルだった件」
2001年8月に設立されたCRI・ミドルウェアは、さまざまなソフトウェアを開発するためのミドルウェアを手がける企業。ゲーム業界で幅広く利用されており、8700以上のタイトルでライセンスが採用されているほか、モビリティ向けでも動画の再生や演出を行なう「CRI Sofdec」、音声をミキシングする「CRI ADX-AT」、デジタルメーターのリアルタイム映像などを描画する「CRI Glassco」といった製品をリリースして、車載製品としても累計1000万台以上に搭載されているという。
また、講演を行なった近藤副部長はもともとセガで業務用、家庭用双方のゲーム開発を行なってきたほか、2D/3Dグラフィックス開発の統合環境「アクロアーツ」の整備にも携わり、「コンテンツダウンロードモデル」対応するアクロアーツはモビリティのSDVやOTA(Over The Air)にも通じる技術だと説明。さらにこれまで自身が手がけてきた業務用カラオケの「精密採点Ai」、知育玩具の「ePICO」、業務用ゲームの「三国志大戦」、モビリティ向けのCRI ADX AutomotiveやCRI Glasscoなどを挙げ、エンタテインメント業界は従来からソフトウェアと追加コンテンツの力が大きく働いて動いており、これはSDVやOTAの考え方を先取りしたものだと解説した。
本題に入るにあたり、近藤副部長はSDVという単語を通常のソフトウェア・デファインド・ビークルではなく、ソフトウェア・デファインド・バリュー(ソフトウェアで定義された価値)と読み替え。自身が追求してきたソフトウェアが生み出す価値について語ることで、ソフトウェアがモビリティの分野でどのようにして価値を生み出すのかを解説した。
ソフトウェア・デファインド・バリューで価値を生み出す場合、ゲームなどのエンタメ業界で考えると価値はユーザーの「体験」によって発生すると説明。スマートフォンなどのゲームでは、ゲームアプリに追加コンテンツを継続的に投入することで価値をアップデート。アプリを長寿命化して売り上げの最大化を図っていることを紹介した。
具体例としては業務用カラオケを挙げ、カラオケボックスという「場・状況」で歌を歌うことを「主アプリ」として提供するにあたり、採点ゲームの機能を「追加アプリ」として用意することで、利用者は歌唱技術の向上と可視化を「体験」の価値として楽しむ仕組みになっていると分析。
ハードウェアであるカラオケボックス自体が家庭などと比べて騒音を気にする必要がなく、カラオケボックスごとでも音響設備や歌唱環境などのこだわりで差別化できる。価値の源泉となる楽曲提供は外部の第三者から行なわれて自力で用意する必要がない部分がカラオケの最大の強みであり、ここに採点ゲームなどを使ってユーザーの欲求を刺激して、「前よりも点数が上がった」という自己満足やネット公開で承認欲求を満たす手段としても利用できると例示した。
「SDVはクルマのスマホ化」と表現されることもあるが、例えばスマホのソーシャルゲームは「場・状況」のコモディティ化が進んでいるものの、リリースされるゲームの90~95%が失敗か赤字となり、採算ラインをクリアできるゲームは残る10%程度で、ヒット作として認知されるのは1~2%に過ぎないと紹介。しかし、問題視されているのはヒット作の少なさではなく、どの作品も同様の「成功の法則」を採り入れて制作されているにも関わらず成否が分かれており、「なぜヒットしたのか」という理由が掴めないことで成功してもほかの作品に生かせていないと説明。
業界では新作投入がまるでバクチ感覚になっており、ヒット作が市場を独占して発生した利益を追加コンテンツに投入することで格差が広がり、「ユーザーの総取り」という市場構造になっている点も課題として指摘した。
こういったソーシャルゲームとモビリティでは立場が異なり、まだ当面の間はプラットフォームとなる車両の台数が足りない状況となる。ここからモビリティ業界が「場・状況」を生かす方向に進むのか、スマホのようにコモディティ化を推し進めるのかが戦略の分かれ道になるが、自動車メーカーなどがカラオケや知育玩具、業務用ゲームのようなビジネスモデルに勝ち筋を見出していくことが重要になるのではないかとの考えを示した。
モビリティは移動することで「場・状況」が多彩に変化する点がとくに大きな強み
ソフトウェアが価値を生み出す構造の分析に続き、実際にソフトウェアで価値を生み出す手法についての説明では、体験した人がどのような気持ちを抱くかが価値につながると語り、平常心から楽しい気分にさせるだけではなく、喜怒哀楽やそのほかの感情、欲求を揺さぶって行き交うように発露させることが感動体験を生み、これが価値に結びつく秘訣になると解説。
この例としてはシューティングゲームを挙げ、数多くの敵から激しい攻撃を受ける緊張状態から一時的に状況を緩和。そこから少しだけ難しい攻撃状態が発生するとプレーヤーがミスをする確率が高まり、このコントロールによって「3分で100円を売り上げる」手法をゲームセンターでは実施。これをモビリティに置き換えると、同じように緊張と緩和の状況変化が交通事故につながり、自宅周辺にたどり着いた場面で事故が起きやすくなると紹介した。
また、ゲームセンターでの取り組みとしては、座り心地のよい電動シートの設置して居心地をよくするほか、ゲーム内での育成要素、カードなどをコレクションしていく収集要素を用意して遊び方の幅を広げ、継続して通い続けてもらえる施策も実施。ゲームセンター自体はコモディティ化が進んだ「場・状況」だが、狭い空間で入れ替えの早いゲームでユーザーの回転数を高める方向性に加え、広いスペースで固定層からコンスタントに利益を得る稼働スパンの長い大型筐体なども展開して、敷地内での差別化を行なっていることを説明した。
価値を生み出す仕組みは開発に携わるクリエイター(ゲーム業界ではデザイナー)とエンジニア(ゲーム業界ではプログラマー)の協力によって生み出され、モビリティのSDVでも重要な部分になると強調。それぞれの得意領域や問題解決の手法は異なるが、ゲーム業界では「クリエイターが活躍できる場所をエンジニアが作る」ことがポイントになると考えられているという。
カラオケの精密採点Aiで行なった工夫を実例として紹介。従来の採点ゲームでは採点につながる結果部分を中心に画面表示していたが、精密採点Aiではクリエイターである近藤副部長が「これから歌う次のページが先行表示されると歌いやすい」と着想。このアイデアを、現在のページと次のページをクロスフェードして表示させる技術をエンジニアの技術で実現。クリエイターの想像力とエンジニアの技術力が噛み合ったことで体験価値向上が実現されたとした。
しかし、実際の開発現場では必ずしも上手くいくケースばかりではなく、例えば新しいゲーム機が発表された際、クリエイターはメーカーが公表するハードウェア性能の理想面に、エンジニアはハードウェア性能の現実部分にそれぞれフォーカス。意見が対立した場合、クリエイターの権限が強いと物理的に実現不可能な要求が押し付けられ、逆にエンジニアの権限が強いと開発機材の強化が求められてコスト増につながり、近年の開発費高騰はこの面が影響していると明かしたほか、お金の力で問題解決するとエンジニアとクリエイターの能力や技術が育っていかない点も問題ではないかと指摘した。
こうした問題が起きないようにするためには、まずエンジニアが実機やクラウド上のエミュレーション環境などで開発環境の現実をクリエイターに先渡しで提供。ここでは「クリエイターのやり方で実機が持つ力を理解できるデータ」を提供することがベストだとした。こうすることでクリエイターから現実的なゲーム内容が提案されるようになり、エンジニアと話し合って相互理解に基づいた開発が行なわれるようになる。
このような考え方からCRIでは徹底的なシンプル化で、「統合環境不要」「コンパイラ不要」「プローブ不要」を実現した、デザインツールだけを使うモビリティ向けの開発環境を採用。この開発環境からデータ駆動型のモデルデータを出力してエミュレーション可能なWindows専用デバッガーで完成形まで造り上げ、ボタン配置などの細かなUIをルネサスの「RH850」やインフィニオンの「Traveo2」などで調整して量産化する。
デジタルメーターを納入する先が高級車だけなら高性能なグラフィック向けハードを用意することも可能だが、普及価格帯のクルマや多くの2輪車では搭載するECUの性能にも制限がある。しかし、そういった限られた環境下でも想像力と試行錯誤によって新たな価値提供は実現可能だと語り、例えば昔のゲームは現代と比較すれば映像表現などのレベルも低かったものの、楽しく感動しながらゲームを遊んでいたとふり返り、コンテンツの魅力は必ずしも性能に引きずられるものではないとアピールした。
モビリティでソフトウェア・デファインド・バリューを実現する場合には、移動することで「場・状況」が多彩に変化する点がとくに大きな強みになると分析。強みである「場・状況」に適合するコンテンツ作りが求められるとした。
例えばCRI製のデジタルメーターを「主アプリ」として採用するクルマ向けに、一般道では「追加アプリ」として「塗り潰しマップ」、サーキット走行中には「初心者向けレース管理」などを提供。中央部分のスピードメーターなどは「主アプリ」として固定しつつ、ADASの接近警報や航続可能距離などを表示する両サイドのウインドウの表示内容を「追加アプリ」で変化させることで「体験」の価値を高めていく。
「塗り潰しマップ」ではカーナビ情報などと連動したスタンプラリー機能や踏破状況などを表示して、ADASの接近警報で危険の通知が必要な場合は表示内容を切り替え。「初心者向けレース管理」では車両の速度リミッターなども設定。例えば上限速度を60km/hまでとして安全なサーキット走行を実現し、左右のウインドウにラップタイムやベストタイム、走行位置などを表示。一方でADASの接近警報は動作を続けつつ、表示は変化させないといった使い分けも想定している。
モビリティでは安全性の確保が欠かせないが、とくにサードパーティなどのクリエイターは意識が届きにくい部分でもあり、この点についてはSDV向けアプリ開発の外側で安全性をフォローする仕組み作りをモビリティ業界から提供する必要があるとコメント。そのために、OSの振る舞いによる安全確保、APIの仕様による安全確保、疎結合での安全確保といった手法があると説明し、同日に講演が行なわれたOpen SDV InitiativeにCRIも参画して、安全面も含めた取りまとめ活動を行なっているとアピール。「技術的な安全性と文化的な革新性は両立できる」と述べた。
最後に近藤副部長は、「僕たちは日本が誇るソフトウェアパワーの一端でしかありませんが、モビリティの発展に少しでも寄与していきたいと考えて取り組んでいます」と締めくくった。