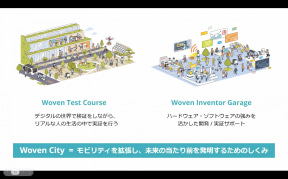ニュース
「第10回 オートモーティブ・ソフトウェア・フロンティア 2025 オンライン」開幕 ウーブン・バイ・トヨタ隈部CEOが基調講演
2025年2月19日 10:53
- 2025年2月18日~20日 開催
SDV時代の自動車ソフトウェア開発とモビリティ社会のこれからを探るオンライン講演会「第10回 オートモーティブ・ソフトウェア・フロンティア 2025 オンライン」(主催:インプレス、共催:名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所)が2月18日~20日に開催されている。
自動車メーカーや部品メーカー、Tier1-2、OEM系ソフトウェアメーカー、半導体メーカー、組み込みソフトウェアメーカーなどで研究開発に携わるエンジニアを中心に、事前登録するだけでZoom/Vimeoから無料参加できるこのオンライン講演会では、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)の概念が広く認識されるようになってきた昨今のソフトウェア開発の最前線で活躍する多彩な講演者が講演を実施。
開催初日の2月18日には、トヨタグループのソフトウェア開発会社「ウーブン・バイ・トヨタ」の代表取締役 CEOを務める隈部肇氏が「モビリティカンパニーへの変革に向けたウーブン・バイ・トヨタの取り組み」と題する基調講演を行ない、WbyT(ウーブン・バイ・トヨタ)が取り組んでいるSDVの実現や自動運転、ADAS(先進運転支援システム)に関連するソフトウェア開発、静岡県裾野市で建設を進めている「Toyota Woven City」の近況などについて解説したので、この内容について紹介する。
基調講演「モビリティカンパニー変革に向けたウーブン・バイ・トヨタの取り組み」
隈部CEOは冒頭でWbyTの概要について語り、WbyTではグローバル本社を東京に据え、米国、英国にもオフィスを展開して世界60か国以上から集まった2200人の従業員が在籍。クルマの知能化を加速させるために必要なモビリティのプラットフォームであり、ユーザーに新たな価値を提供する「Arene OS」、安心・安全な移動を実現していく「自動運転/先進運転支援システム」、モビリティの未来に向けた革新的なテクノロジーやビジネスモデルを開発するグロースステージ企業に投資する「ウーブンキャピタル」、実証実験を行なって“未来の当たり前”を発明していくモビリティのためのテストコースである「ウーブンシティ」という4つの事業領域に取り組んでいると説明。これらの取り組みを通じ、WbyTはモビリティカンパニーの変革を目指していると語った。
モビリティカンパニーの変革を目指すWbyTだが、一方で「モビリティカンパニーという言葉に正解はないと考えている」と語り、現会長の豊田章男氏が2009年6月に社長に就任した際、「もっといいクルマをつくろう」と発言したが、この「もっといいクルマ」の具体的な回答はなく、これに対してトヨタグループの1人ひとりが真剣に考えた結果としてさまざまなクルマが商品として生み出されてきたが、モビリティカンパニーについても同様で、「モビリティカンパニーとは何か」「モビリティを通じてどのように幸せを提供できるか」について従業員1人ひとりが悩み、考えてさまざまなプロダクト開発に取り組んでいると述べた。
そんな取り組みの具体例として、建設が進んでいるウーブンシティはトヨタ自動車が運用しているクルマのテストコースとは異なり、これまでにない“人の心をも動かすモビリティについて試すテストコース”として、自動車以外のモビリティについてテストを行なう場所になり、実際に人が暮らす環境内で、リアルな感想を聞き取りながら実証する「街の形をしたモビリティのテストコース」となっている。
ウーブンシティの第1段階である「Phase1」の建物は2024年10月に竣工。現在は内装工事やインフラ工事の段階に進み、今秋以降にテストコースの街としての稼働を始めて実証実験をスタートさせるための準備が続いているという。
1月に米国で実施された「CES 2025」で豊田会長が行なったウーブンシティについて解説するプレゼンテーション動画を紹介したあと、ウーブンシティで取り組む具体的な内容を説明。トヨタではこれまでクルマを進化させることで交通事故ゼロと安心・安全な社会の実現を目指してきたが、ウーブンシティではモビリティに加えてヒトやインフラも一体で検討。例えば、「信号の時間配分を変える」「横断歩道の場所を変える」「建物の角を丸くして死角を減らす」といった工夫をし、安全・安心につなげる検討を行なっていく。
これに加え、クルマは実際に走行している時間はわずか5%で、残る95%は走行していないことにも着目。この稼働していない時間の有効活用も今後のモビリティ拡張に向けた糸口になると考えていると述べた。
人が暮らす街であり、モビリティを拡張して“未来での当たり前”を発明していく仕組みとして位置付けるウーブンシティではデジタル世界での新技術の開発・検証と人が生活するリアルワールドでの実証を連動させる「ウーブン テストコース」、ハードウェア、ソフトウェアの強みを生かした開発と実証サポートを行なう「ウーブン イノベーターガレージ」を展開。
ウーブンシティは静岡県裾野市にあるリアルの市街地に加え、デジタル空間に同様の環境を再現したデジタルツインを用意。新たな街づくりをリアルとデジタルの両面から整備していることが大きな特徴となっている。新しい製品やサービスを開発するインベンションをまずはデジタルツインでのシミュレーションで行ない、これをトヨタのもの作り技術で実際の製品につなげ、リアルワールドで行なった実証と改善の結果をシミュレーションにフィードバックするというサイクルで改善を重ねていくことで、開発のリードタイム短縮を実現していく。
AIプラットフォーム開発にもデジタルとリアルの融合が活用され、映像データとAIを組み合わせて人や物の動線理解、人の行動理解などを行なうAI基盤技術であるビジョンAIの開発にも使って分析の自動化や省人化を進めている。このほか、街のインフラや人のデータを連係させて分析する「ハブ」、データ活用でAIやアプリなどを開発するUIなども提供していくという。
新たな街づくりとなるウーブンシティは発表後から大きな反響を呼び、ウーブンシティのWebサイトには企業や個人から6000件を超える問い合わせが寄せられたという。この中からウーブンシティで実証可能と感じた提案について相手方との検討を進め、すでにサポートをいただいているエネオス(ENEOS)、NTT(日本電信電話)、リンナイに加え、1月のCES 2025でダイキン工業、ダイドードリンコ、日清食品、UCCジャパン、Z-KAI(増進会ホールディングス)の5社とInventors(インベンターズ/発明家)として契約締結したことを発表。
協力に向けた話し合いでは実証する具体的な内容に加え、「未来の役に立ちたい」「自分以外の誰かの役に立ちたい」という思いを共有できるか、目指す未来が同じなのかについて議論を重ね、各社が持つ強みとトヨタの強みをかけ算することで今よりもよい未来を実現したいと考えたという。
また、ウーブンシティで実証したい案件についてのコンタクトは引き続き受け付けており、今後はInventorsの対象をスタートアップ企業や大学・研究機関といったアカデミアにも拡大していく。
トヨタのモビリティ変革の中核であるウーブンシティはモビリティのテストコースであり、街や生活の観点からモビリティを拡張していくウーブンシティに対し、ソフトウェアプラットフォームのArene OSや自動運転は自動車の観点からモビリティを拡張する。
また、今ではバズワードとなっているSDVについては、トヨタではユーザーに寄り添い、交通事故ゼロの社会を実現する技術だと考え取り組んでいるという。そんなSDVの基盤となるArene OSは、ユーザーに提供する価値を継続して高めていくプラットフォームであり、ユーザー体験につながるアプリやサービスだけでなく、車両のソフトウェア開発や評価を効率的に行なうためのツール、サードパーティの開発者向けとなるSDK(ソフトウェア開発キット)開発などにも取り組んでいる。自動運転では交通事故ゼロに加え、すべての人に自由なモビリティを提供する「モビリティフォーオール」を実現する技術として開発が進められている。
これらのプロダクトを使い、人、クルマ、インフラが一体としてつながり、安心・安全なモビリティ社会を実現すること、そして幸せの量産に貢献することがWbyTの役割だと定義した。
このほかトピックとして、宇宙でのインフラ構築を目指す日本のスタートアップ企業「インターステラテクノロジズ」とWbyTが資本業務提携を結んだことについて説明。
トヨタでは2020年から人材交流などを同社と行なっており、宇宙を通じて持続可能な地球の未来を実現する両社の思いが合致していると感じるようになったという。また、非常に複雑なもの作り技術の結晶であるロケット開発にトヨタの技術を活用することで開発を加速させられるのではないかと考えたことから、70億円を出資することに加え、トヨタが培ってきた知見や技術などを提供することで、同社のロケット量産化をサポートしていくことになった。隈部CEOも同社の社外取締役に就任して、もの作りサポートとコーポレートガバナンスの強化を推し進めていく。
この提携で陸海空に加え、モビリティのスコープを宇宙まで広げ、モビリティの拡張につなげていくとした。
WbyTはトヨタがモビリティカンパニーに変革するにあたってタグボートとしての役割を果たしていきたいと語り、自動車の量産やトヨタ内でのルールに収まらず、新しいやり方を実装してトヨタに対して貢献し、トヨタと共に移動の未来を切り開いていく。結果としてトヨタグループとしてできることを増やしていくことを目指していると方針について語った。